竹中 治堅 政策研究大学院大学教授

1990年代以降、日本の政治構造は大きく変貌した。93年に55年の結党来初めて自民党が政権を失い、いわゆる55年体制が崩壊し94年に政治改革が実現した。選挙制度が変更され、政治資金の規正が強化された。2001年には省庁再編が行われ、首相の法的権限と補佐体制が強化された。改革の結果、政党システムは変化し首相の指導力は強まったということになる。こうした一連の変化を理解するために役立つ、15冊の本を紹介したい。
理解の前提として、90年代以降の政治過程の全貌を頭に入れることから始めよう。最初に、『平成政治史』全3巻で、竹下登内閣から野田佳彦内閣に至るまでの政治プロセスをたどる。それ以前の55年体制下の政治は次の2冊で把握したい。『自民党』で55年体制下の自民党政権の歩みを振り返ることができる。加えて、『岸信介証言録』では岸信介元首相が生前のインタビューで保守合同の経緯や岸内閣について回想している。本書は政治家の処世訓も随所に現れていて興味深い。

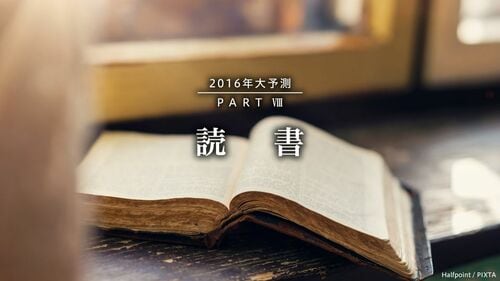































無料会員登録はこちら
ログインはこちら