第一線で活躍する社会人を「副業先生」として起用した学校の本音 高知高専と英理女子の事例に見る利点と課題
「自分自身にロールモデルがおらず、もがき苦しんできたこともあり、OBの一人として高専生のキャリアデザインを応援したいという思いで応募しました。また、私が専門とするサイバーセキュリティー分野において、優秀なエンジニアを安定的に再生産していくことは社会課題であると捉えており、そこをライフワークと考えていることも大きな動機です」(林氏)
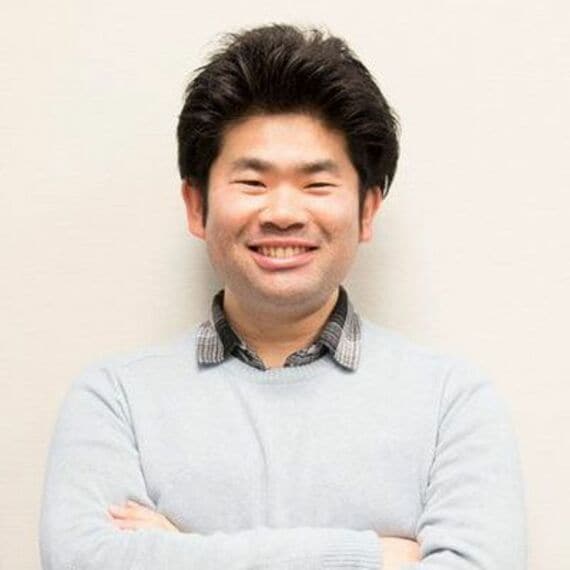
2002年に大手サイバーセキュリティー対策ベンダーへ入社。1年間の米国勤務から帰国後、日本国内専門のマルウェア解析機関を経て、先端脅威研究組織へ。単独で日本部門の立ち上げを行う。現在は、日本におけるサイバー犯罪対策、とくにオンライン詐欺を専門とした調査・分析業務を担当。研究諸機関や法執行機関における窓口として、情報共有や共同研究なども実施。警察庁「サイバーセキュリティ政策会議」委員。1998年3月、育英工業高等専門学校(現:サレジオ工業高等専門学校)卒業。2002年3月、電気通信大学電気通信学部電子物性工学科卒業。11年3月、金沢工業大学大学院知的創造システム専攻修了
(写真:林憲明氏提供)
林氏は、これまでもサイバーセキュリティーの啓発活動の一環として、高校でシリアスゲーム開発の授業を行ったり、JNSA(NPO日本ネットワークセキュリティ協会)でゲーム教育ワーキンググループに立ち上げ期より参画したり、社外での教育活動にも複数携わってきた。そんな経験も踏まえ、高専生の社会的価値を高めるために必要なことについてこう語る。
「米国などでは『KSA』、すなわち、knowledge、skill、attitudeの3つが教育で伝えられることのすべてだといわれています。私はこれを日本語で、知識、技能、心得と捉えており、優秀な人材の育成に必要な要素だと考えています。高専生は知識と技能に優れていますが、今DX(デジタルトランスフォーメーション)が浸透する現場で重要視されているのは心得。副業先生としては、とくにこの心得を伝えていければと思います」
林氏は、半期に2コマ、4年生を対象とした科目「情報工学実験Ⅱ」を担当。2021年度は40名強の学生にセキュリティーの脆弱性診断を体験してもらう授業を行い、ヘルプの教員とティーチングアシスタントの5年生と共に進めた。コロナ禍もあり、実施は主にリモート。授業以外でも学生からリクエストがあり、部活動としてのレクチャーもしたという。
「今の会社に20年以上勤めていますが、これを機にピュアな気持ちを思い出すことができました。とくに学生が学び合い課題解決する姿を見て、自分の仕事の場でも生かしていきたいと思いました」と、林氏は話す。
林氏は、説明動画を流しながら学生と対話するなど、オンラインとリアルを融合した授業を心がけており、21年度はほかの高専教員の要望に応え、高知高専で使った授業コンテンツの提供も行った。「22年度も、どんな教員でも再現できる授業内容にしたい」と話す。
一方の高知高専も、大きな成果を得たようだ。学生の反応はとてもよく、教員もよい刺激を受けることができたという。高知高専ソーシャルデザイン工学科教授の岸本誠一氏はこう説明する。






























