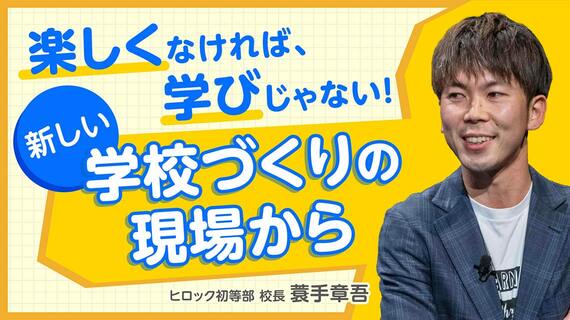このシステムの中では、自分が自由に教育実践をすることで、意図せずして誰かを傷つけてしまいかねない。それでも「子どもが学びを楽しめる場」を実現してみたい。小学校に選択肢を生み出すことで「子どもも、親も、学校も、教師も」もっと幸せになれるはず。そんな思いから、安定を捨てて学校をつくる決意をしました。
勉強が苦行なのは「学校システム」の責任
今回の副題は「学びを捉え直す」です。そもそも学びとは、脚色して楽しくするものでも、価値づけをして意味を持たせなければならないものでもなく、単純に、生物的に心地よいものだと信じています。
地球上に住むあらゆる生物は「種の保存」がDNAに組み込まれていて、そうなるためには「成長」を「快」と結び付ける必要があったわけです。例えば、自然界の動物を見ていると、誰が押し付けるでも、意義を説くでもなく、喜々として動きを学び、狩りの仕方を覚え、棲みかの作り方を会得します。
これらは人間もまったく同じです。赤ちゃんを見ているとわかりますが、彼らは誰が押し付けなくても言語を話すようになるし、危険を冒してまで歩こうとするのです。誰一人として、将来のために言語を学習したり、我慢して歩く練習をしたりする赤ちゃんなんていませんよね。成長や学び、勉強は、そもそも楽しくて仕方がないようにDNAに組み込まれているものなのです。
にもかかわらず、「勉強が苦行」で当たり前と考えてしまっているのは、おそらく学校システムの責任だと思うのです。よい大学、よい会社に就職することが幸福の一本道だと信じ込み、不安と競争の災禍に勉強や学びを位置づけてしまったがゆえの、いわば「誤学習」といえるのではないでしょうか。これはあくまで私的な仮説ではありますが、その答え合わせをするためにもヒロック初等部を立ち上げようと思ったのです。
順位づけも競争もない。授業時数や到達度の縛りもない。内容も、子どもの興味関心を出発点にし、子どもたちは互いの年齢さえ気にならない。そんな学びの空間をつくり上げれば、きっと人は誰しも「学びたくて仕方ない」という本来の姿に戻るのではないでしょうか。
そんな学びの場をつくりたくて仕方ない教育オタクが、連載をスタートさせていただきます。読者の皆さんと共に「心地よく」学び合い、成長していきたいと考えています。
(写真:蓑手氏提供)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら