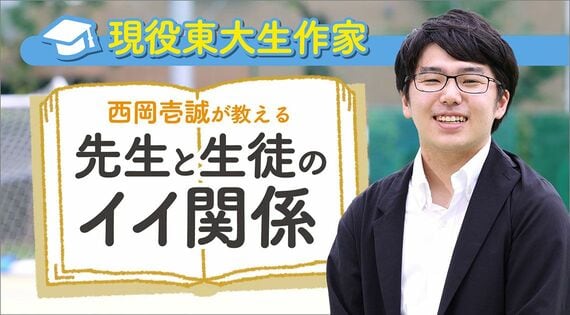これだと、後から振り返りができなくなってしまいます。「昨日のやつ進んだの?」「え?まあ……」と、ぼんやり「やるにはやったけど、十分かどうかはわからない」といった状態になってしまうのです。
もっと顕著なのは、テストの点数です。多くの学生に「次のテスト、いい点取りたい?」と聞くと、みんな「取りたい」と答えると思います。でも、「じゃあいい点って何点?」と聞くと、大抵「え?」と考え込んでしまいます。
60点でいい点だと思う科目もあれば、80点じゃないといい点じゃないと思っている人もいる。そんな中で、実は「いい点を取りたい」と思っていても、「70点取りたい」のように目標点数を数値化していない場合が多いんですよね。
こうなると難しいのが、振り返りです。「今回の数学、どうだったの?」「え?まあまあだった」というように、具体的な振り返りができないのです。「あと3点で目標点数だった!あの問題さえ合っていればなー」と答えられる人がいれば、その人はそのテストでどこが自分の弱点になっているのか、何が駄目だったのかをしっかり理解できるようになります。
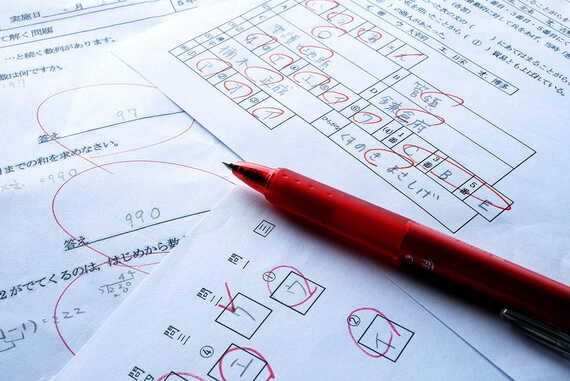
しかし、なんとなくいい点を取りたくて、なんとなくいい点を取れてしまうと、何にも振り返るモチベーションが湧かず、「まあいいか」で終わってしまう。これではテストを受けた意味がなくなってしまうのです。
だから必要なことは、目標を点数で決めてもらうこと。そして、あえて言葉を選ばずに言うなら「失敗してもらうこと」です。なあなあで「これくらいでいいか」では、いつまで経っても成長できません。しっかり、「これが足りていない」と言えるようになっていなければ意味がないのです。
いかがでしょうか? コーチングというのは投げっぱなしで「そんなことは自分で考えろ!」という姿勢では難しいものです。しっかりと主体的に考えてもらえるフォーマットを作ってあげることも必要なのです。そのために「分解」と「数値化」を意識して指導してみてください!
(注記のない写真:Fast&Slow/ PIXTA)
執筆:西岡壱誠
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら