プログラミング授業の作り方と教材選びの要諦 ロボット?アンプラグド?教科との連携は?
こう見ていくと、PCを使わない「アンプラグド系」がプログラミング教育の入門編としては適していると考える人も多いかもしれない。実際、ICT環境がなくてもプログラミング教育を導入できることもあって、いち早く導入した教育委員会や学校も少なくない。しかし面白いことに、授業の組み込み方では意見が分かれた3氏はアンプラグドの意義を認めつつも、そろって消極的だ。それぞれの意見を紹介しよう。
「残念ながら失敗することが多いです。ロボット役を児童がやると、指示どおり動いてくれなかったり、正しくプログラミングできているかの確認に時間がかかったりと、いろいろなことを想定しなければならないので先生の準備が非常に大変です」(加藤准教授)
「アンプラグド自体は、すばらしい手法だと思います。しかし、子どもたちは大人が思うよりも創造的で、予想外の行動をするんですよね。それに対し、『コンピューターとしてどう反応するか』を先生が理解できていないといけないので、難易度は非常に高くなりオススメしていません」(利根川氏)
「今は1人1台情報端末が配備されることが決定しています。プログラミングはコンピューターを使わないとできませんし、今後子どもたちはコンピューターがつくる新しい社会を生きていくんですから、それを使う授業を優先するべきではないでしょうか」(松田氏)
わかりやすさなら「ロボット」、導入しやすさなら「アプリ」
では、「アプリ系」「ロボット系」に関してはどうか。「ロボット系」はプログラミングソフトを用いるため、「アプリ系」の発展形ともいえるが、プログラムの結果がパソコンのモニター画面ではなく具体的なモノの動きとして見えるのが特徴だ。その効果を加藤准教授は次のように説明する。
「とくに低学年の場合、抽象的な考え方ができないので、目に見えて動くロボットやランプといった具体物があったほうがいいと思います。子どもたちの“食いつき”もいいですし、理解もしやすくなります」
「ロボット系」を活用した学び方を絵本の形で著したのが松田氏だ。その絵本である『学校・家庭で体験ぜんぶIchigoJam BASIC! プログラミングでSTEAMな学びBOOK』は、LEDライトやロボット、ドローンなど、小学1年生から中学生まで学年に合わせた学びがわかりやすくまとめられている。特徴的なのは、テキストプログラミングへ自然に移行できるようになっている点だ。
「1・2年生はカード型ビジュアル言語を使い、3年生からはテキストに移行し、6年生ではサイバー空間のプログラミングができる設計にしています。IchigoJamを用いていますが、これはプロも使うプログラミング言語『JavaScript』ともコマンドや構文が似ていますので、中学・高校で学ぶ高度なプログラミング教育にも対応しやすいと思います」(松田氏)
他方で、「ロボット系」はどうしても有償となってしまい、導入までに手続きと時間を必要とするのが難点だ。「セーフティネットとしての公教育」でプログラミング教育をあまねく展開する観点で、即導入可能な「アプリ系」のプログラミング教材を提供しているのが、利根川氏が代表理事を務める「みんなのコード」だ。
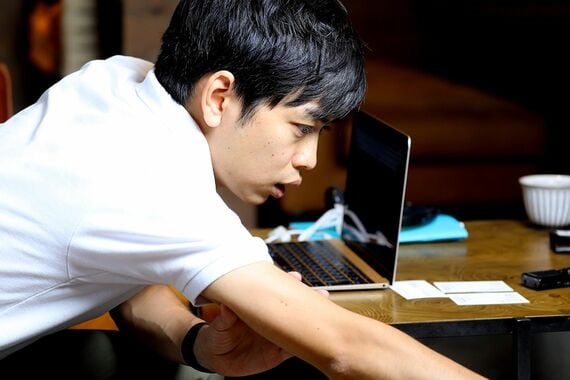
慶應義塾大学経済学部卒業後、森ビルを経て、ラクスルへ。その後、特定非営利活動法人みんなのコード設立。著書に『先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本』(翔泳社、共著)、『なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか-はじまる「プログラミング教育」必修化』(技術評論社、共著)がある
(撮影:今井康一)






























