パナのスマホ、どん底からの復活はあるか 個人向けは風前の灯火
「最大の変化点はiPhone(アイフォーン)の登場ですよ」。パナソニックの携帯事業関係者は、苦境に陥った背景を振り返る。
「ガラケー」や「フューチャーフォン」などと呼ばれる従来型の携帯電話が全盛だった1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本の携帯電話端末メーカーは飛ぶ鳥を落とす勢いだった。パナソニックも同様で、携帯電話端末の開発や生産、販売を手掛けていた松下通信工業(現・パナソニックモバイルコミュニケーションズ)は2000年当時、時価総額が本社の半分近くにまで拡大。「会社の屋台骨を支えていた」(パナソニック関係者)ほどの優良企業だった。
開発費100億円でも回収できたガラケー
当時の携帯電話端末は、ドコモなどの通信業者が提示する仕様に基づいて開発・製造し、通信業者に買い取ってもらう、いわば“特注品”。端末メーカーは心臓部のOS(基本ソフト)も含めて自社で開発するのが一般的で、1機種当たりの開発費は100億円単位に上った。それでも1機種で年間200万台以上の販売が見込め、「十分に開発費用を回収できた」(パナソニック関係者)。

しかし、2000年代後半、米アップルからiPhoneが華々しくデビューした後に始まった携帯端末の“スマホ化”によって、そうした時代は過ぎ去っていく。
スマホは理屈上、CPU(中央演算処理装置)や液晶パネルなどの汎用部材を組み合わせ、無償のグーグル製OS「アンドロイド」をインストールすれば出来上がる。スマホは「サーバーにあるものを見るための箱に近い存在になった」(携帯電話業界に詳しいアナリスト)。
日本ではドコモが主導し、独自の携帯端末用OS開発に向け、業界団体「LiMo Foundation」を設けて、アンドロイドに対抗。パナソニックも陣営に加わったが、この対応に時間を取られ、アンドロイド端末投入の遅れにつながった。パナソニックのスマホは結局、国内市場で最後発となり、ブランドの確立に手間取った。これがツートップから外れた理由の一つでもある。




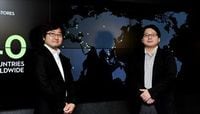




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら