やりたいことを後押しする文化がある…社会に出て「花開く人」を続出する学校は何が違うか?野沢北高校"探究学習の授業"をのぞいてみた
また、探究の野沢北オリジナルテキストは、生徒と職員がクラウド上で共有。授業用のレジュメは副担任が作成するようにし、できるだけ特定の教員に負担が集中しないシステムを構築しました。
部活動も「探究」に
現在、同校には1学年200人(普通科160人、理数科40人)が通っています。同校の生徒たちは入学したての4月には、探究学習に向けてのガイダンスを受けます。
そして、5月から1月にかけて「探究基礎」の授業を受け、その後「探究」移行、学年をまたいで2年次の9月に中間発表、その後12月まで継続的に活動を進めて探究発表会を開催、3年次の個人研究、論文作成につなぎます。
この10年で蓄積した教員たちの知見は、今でもオリジナルテキストのブラッシュアップという形で進化しています。こうして進めてきた探究学習、授業として行うのは週に1コマだけですが、探究は授業の中だけで終わるものではありません。見つけた学びの種は頭の中に常にあるので、部活動さえも探究的な学びにつながることがあるのです。
〇週1コマ(原則月曜日7限目)で実施
〇1年生:探究基礎(5月〜1月)→本格探究(2月〜)
〇2年生:探究活動を継続、12月に発表会
〇3年生:論文作成
陸上部で競歩に取り組むある生徒は、人体動作向けマイクロセンサー技術を使った製品などを開発する地元のベンチャー企業、マイクロストーン社と共同で、自身の歩き方を科学的に分析することに。3台のカメラを使用し、歩行フォームを徹底的に研究した結果、最適な歩行方法を見いだし、競技力を大幅に向上させることに成功、北信越ブロック新人大会で優勝、北信越の代表選手となり見事インターハイ出場を果たしました。
「この企業の開発部長が本校の卒業生だったことがきっかけで、この共同研究が実現しました。後輩たちもこの研究をさらに発展させようと意欲的に取り組んでいます」(柳沢校長)

生徒一人ひとりの興味と情熱を尊重し、伴走する教育を目指し、自分たちに合ったやり方を模索しながら作り出してきた探究学習。大学や研究機関が少ない地方の学校でも、創意工夫次第で豊かな学びを実現できることを示すモデルケースといえるでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

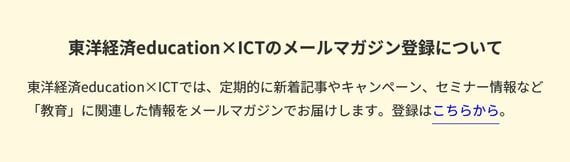































無料会員登録はこちら
ログインはこちら