再生医療製品には、生きた細胞からつくるため品質が安定しにくく、患者の体内に長く残ることが多いため安全性も年単位で見ないとわからない――といった従来の薬にはないハードルがある。基礎的な研究を終え、製品の実用化を目指す段階の難しさを表す言葉に「死の谷」があるが、早期承認制度は、再生医療特有の事情を考慮し、死の谷に一定の条件を満たした再生医療製品だけが渡れる「つり橋」をかけるような制度といえる。
早期承認を受けた企業は、定められた期限内に市販後のデータから安全性と有効性を検証し、本承認を受けなければならない。しかし、早期承認の第1号となった重症心不全治療用のハートシートは2024年7月、「有効性が示されていない」として、本承認の申請を却下された。
また、遺伝子治療製品コラテジェンで3番目の早期承認を受けた大阪大学発のベンチャー、アンジェスは、「市販後調査で臨床試験の成績を再現できなかった」として本承認の申請を取り下げている。早期承認されたほかの3製品はまだ本承認の申請期限を迎えていない。
再生医療に特化した早期承認制度は海外でも例がなく、海外からは違和感をもって受け止められてきた。
「臨床試験の対価を患者に払わせる未実証の制度」(英科学誌ネイチャー)、「ある国での規制緩和は世界レベルで再生医療分野に予期せぬ有害な結果をもたらす可能性がある」(米科学誌サイエンス)などの批判を受けてきた。
ネイチャーは「将来、早期承認制度によって承認された製品に効果が見られないということがきっと起こる」とも書いたが、制度の最初期に恩恵を受けたハートシートとコラテジェンの2製品はまさにその予言どおりになってしまった。せっかく用意した「つり橋」を渡り切れなかったということだ。
改めて当時の批判を真摯に受け止め、制度の検証をすべきときかもしれない。

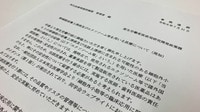































無料会員登録はこちら
ログインはこちら