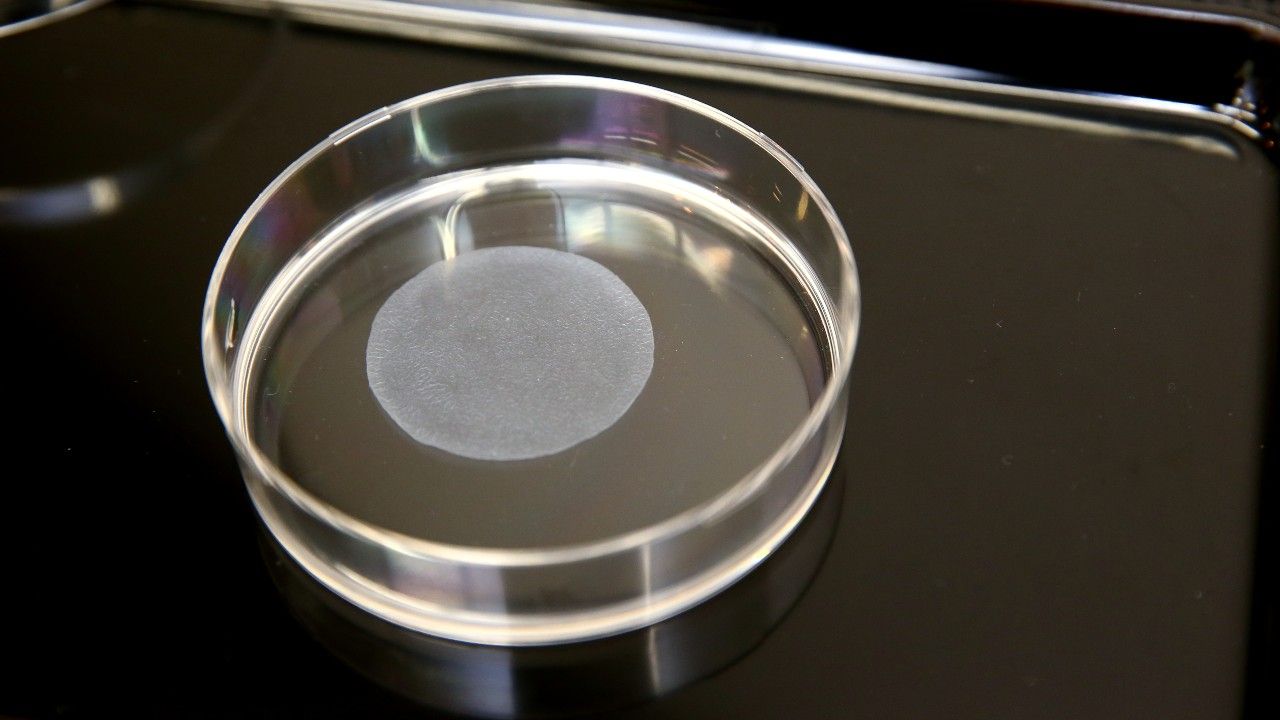
人工多能性幹細胞(iPS細胞)由来の再生医療製品で承認申請が相次いでいる。
大阪大学発のベンチャー、クオリプスは2025年4月、重症心不全の治療に用いる心筋細胞シートの製造・販売の承認を厚生労働省に申請した。患者8人に移植した治験(臨床試験)の結果を受けての申請で、承認されればiPS細胞を使った世界初の製品になるとみられる。同社はアメリカでも治験の申請をする予定で、準備を進めている。
また、同じ4月、京都大学iPS細胞研究所の研究チームが、iPS細胞から作った細胞をパーキンソン病患者7人の脳に移植した治験の結果を発表した。2年間の経過観察で安全性を確認し、4人では症状の改善が見られたという。これを受け、治験に協力した住友ファーマが2025年8月、細胞製品の承認申請をしている。
慶応大学などの研究チームも2025年3月、脊髄損傷の患者4人にiPS細胞由来の細胞を移植した臨床研究の成果を学会発表した。
こうしたニュースを目にして、iPS細胞による再生医療の実現がすぐそこまで来ていると感じた人もいるかもしれない。だが、過度な期待は禁物だ。有効性を見極めるには症例数が少なすぎるし、一歩引いてみれば、再生医療を取り巻く現状にはいくつもの課題がある。
再生医療に特化した早期承認制度
今回申請された心筋細胞シートやパーキンソン病治療用の細胞は、どちらも企業側が「条件及び期限付き承認制度(以後、早期承認制度)」の適用を想定している。安全性が確認され、有効性が「推定」されると市販が許可され、保険適用にも道が開かれるという制度で、再生医療を後押ししようと2014年に創設された。


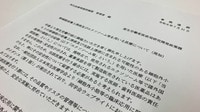






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら