"内申点で不利"な「不登校の中学生」、ベストな進路を勝ち取る「戦略的高校受験」の秘訣 全日制普通科や通信制に落とし穴、注意点は?
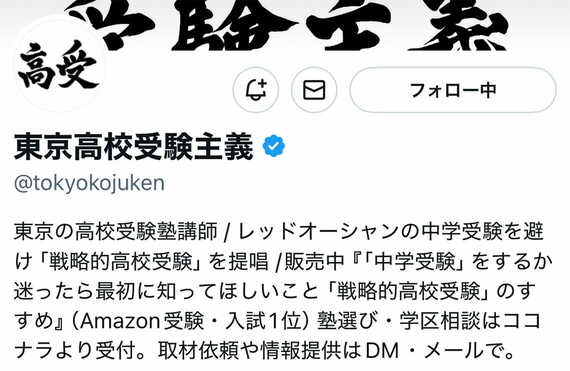
(写真:Xより)
さらに、都立高は正規教員が多く、指導の質が安定している。また、発達特性のある生徒向けに「コミュニケーションアシスト講座」や「通級指導」なども用意し、民間であれば数10万円はかかる専門的なプログラムを30回以上にわたって無償で提供している。こうした教員体制の安定や公的支援の充実も、都立定時制を選ぶメリットと言える。
一方、私立の広域通信制高校では、非常勤講師が大半を占め、教員の質が不安定なことがある。実際、起立性調節障害のある教え子が広域通信制に進学したが、1年間で担任が数回入れ替わり、継続的な支援を受けることが難しかったという。この学校は芸能人を起用し派手な広告を展開しているが、教育の中身が十分に整っているとは言いがたいと感じている。
文部科学省の調査では、広域通信制高校における不適切な運営の事例が多数報告されたため、質の担保のための施策が検討されている。進路選択に当たっては、そうした動向も注視したい。
このほか東京都には「エンカレッジスクール」という都立高校もある。全日制高校でありながら、小・中学校時代に勉強についていけなかった子たちのために、学び直しの機会を与えてくれる。2人担任制や集中力の持続する30分授業、多様な体験学習などを提供し、軽度の知的障害のある子の入学も多いという。
エンカレッジスクールの練馬工科高校に通うお子さんの保護者によると、積極的に宿題や課題をこなすようになり、自立と自信が芽生えたという。自分と同じような子たちが周りにたくさんいる学校生活がとても居心地がよいとのことだった。全日制高校への進学が学力面で不安があるという子は、エンカレッジスクールの専門学科を回ってみてほしい。
また、この記事の執筆中、嬉しいニュースが飛び込んできた。都立深沢高校(世田谷区)が、新しいタイプの全日制高校として生まれ変わるというのだ。同校は登校時間を午前8時半から10時半の間で選べるほか、オンデマンド形式の授業も単位として認定される。入試制度においては、学力検査と内申の比率を7:3または10:0から、得点の高いほうが自動的に採用される仕組みとなる。不登校の子どもを持つ保護者からは、期待の声が相次いで寄せられている。
入試制度などに課題は残るものの、東京都は公的にも不登校生徒を支える仕組みは徐々に整いつつある。全国でも不登校生徒に対応した施策や学校が次々と誕生しており、選択肢は確実に広がっている。
高校受験に関わる者として強調したいのは、情報をしっかり集めて適切な進路を選べば、不登校は決して将来を閉ざすものではないということだ。
(注記のない写真:Mills/PIXTA)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら