続けて、「ほとんどの宗教が信者たちを誰もが直面するのを恐れているものに向き合わせる。死すべき運命、死、病、喪失、不確実性、苦しみ――人生は常にちょっとした災難であるとでもいわんばかりに」と述べ、「宗教は災難への準備――日々の災難をただ生き延びるだけでなく、それを落ち着いて行い、冷静さと利他主義でもって対処させる装置――と見なすことができる」と主張した。
このくだりにおいても、『私が見た未来 完全版』と奇妙に響き合う。「大切なのは、準備すること。災難の後の生き方を考えて、今から準備・行動しておくことの重要さを改めて認識してほしい」と書かれているからだ。
ソルニットのいう宗教は、社会を揺るがすほどの巨大な災害という危機を外部から注入してもらうことで、自らの最良の部分が覚醒させられ、その潜在していた力量がいかんなく発揮され、通常ではあり得ない物事を次々に成し遂げることができる――いわば「災害による自己変革」への期待に支えられていることは間違いない。
予言ブームに乗るわたしたちの熱狂と課題
自己啓発文化の視点から捉えれば、それは「自己啓発の手段としての災害」と位置付けることができるだろう。
この圧倒的ともいえる受動性は「世直り」とまったく同じ性質のもので、内部からの契機は一切存在しない。「災害待ち」と言っても過言ではない。
このように見ていくと、予言ブームに乗っかってしまうわたしたちの熱狂の正体が明らかになる。と同時に、それが負っている課題の深淵も浮き彫りになってくる。
なぜ、日々の暮らしにおいて「それ」ができないのか、という率直過ぎる問いがせり上がって来るのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

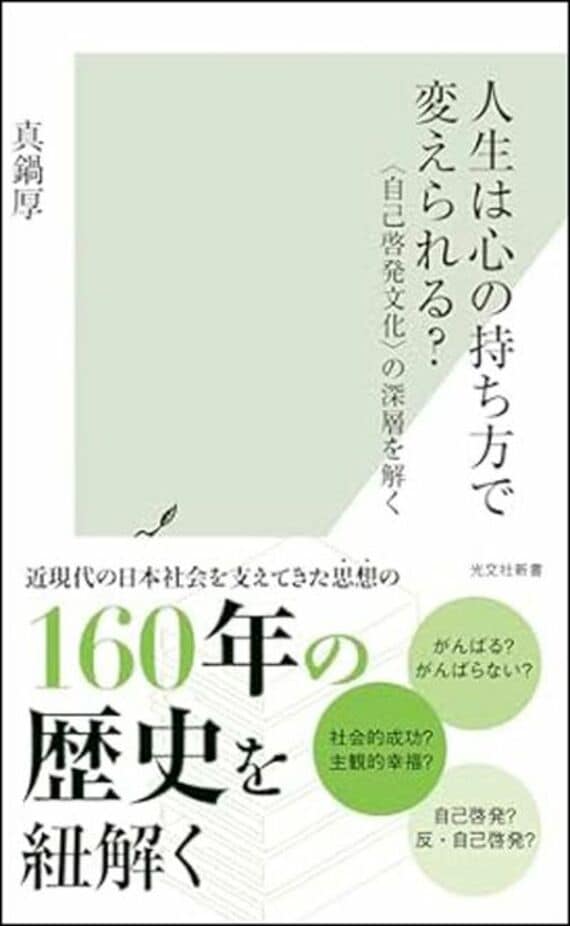






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら