小学校受験で「泣く宇宙人」「なりたい虫」?人気校の傾向と出題例、3つの対策とは 注目は「体験学習」「大学一貫」「出願しやすさ」
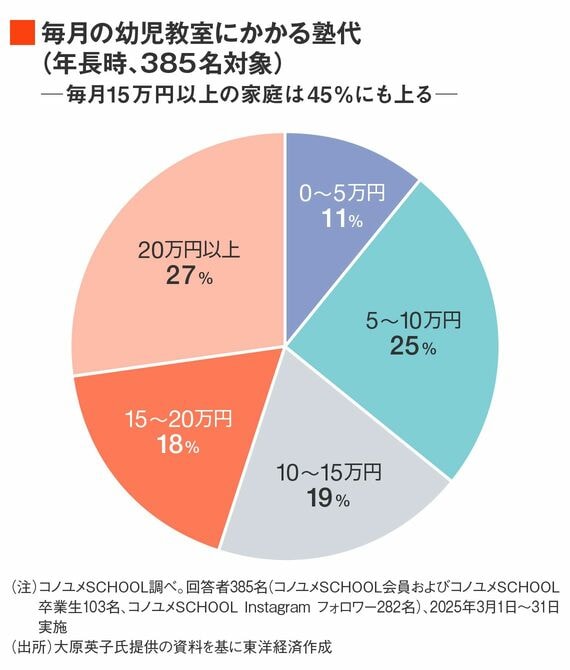
ある家庭では、幼稚園や保育園が終わると、すぐにタクシーに乗せて次の幼児教室へ直行。分単位でスケジュールをこなすその様子は、まるで売れっ子アイドルのようです。
さらに、小学校受験でよく問われる「好きな生き物」や「大人になったらなりたいもの」といったテーマについて、親が答えを決めてしまうケースも見られます。もはや親がプロデューサーとなり、子どもの本来の個性とは異なるキャラクターを演じさせている家庭すらあるのです。
「子どものために」と始めた受験が、いつの間にか親の期待が先行し、子ども本来の姿が見えなくなってしまう。親が追い求めているのは、「合格する子ども」という虚像であり、そのために右往左往するうちに、本当に大切なものを見失っているのかもしれません。こうなってしまうと、「もっと子どもを見て」「子どもの元気がなくなっているよ」という周囲の声も、もはや耳に届かなくなってしまうのです。
子どもの「課題解決能力」が問われる試験
親たちは自分の受験経験を当てはめて、机に向かって勉強する時間を重視していますが、小学校受験は幼児の受験。家庭の生活の中で、何を学び、子どもたちに時には失敗経験も経てどのようなことを学ばせている家庭か、が問われています。
例えば、倍率10倍以上の人気私立小学校である慶應義塾横浜初等部の2025年度入試(2024年11月実施)では、こんな課題が出題されました。

(画像は筆者提供)
ショッピングモールで困っている人がいます。ショッピングモールで売っているものでその困っている人を助けます。困っている人を助ける道具を作りましょう。
その人が何で困っているかも自分で決めましょう。
幼児教室通いに追われるあまり、「ショッピングセンター」が何かすらわからない子もいます。仮に知っていても、どのような人が困るのか、どんな助けが必要なのかを想像できないこともあります。
私立小学校の先生はよく「年齢相応の体験、知識、成長をしているかを確認している」と言います。学校側は、受験準備に費やす時間よりも、日常生活の中で自然に培われる経験を重視しているのです。
またその後はこのような流れがありました。
・先生たちが困っている人を演じているので、声をかけて助けてあげる
・図書館がどこかわからない人や荷物を運べない人、転んだ人などがいる
本番の試験では、困っている人がいることがわかっていても、自分から話しかけることを躊躇している子が多くいたようです。確かに生活の中で、困っている人に声をかける経験はあまりなく、それが見知らぬ大人だったら、なかなか難しいですよね。
親が、例えば電車でお年寄りに席を譲る、物を落とした人に声をかける、など困った人を助ける実践をしていてこそ、子どもが困った人を助けようと思うのではないでしょうか。
子どもが主体的に動けるようになる、3つのポイント
小学校受験の対策として一番大事なことは、子どもが自分で考え、行動する力を育てること。そしてこれは、受験の有無にかかわらず大事なことだと思います。便利な世の中になり、子どもが何かにつまずいたときにすぐに手助けできる環境が整っています。
































