今後どうしていくのか
では、どんな対策が必要だろうか。これまで見てきたことから、やるべきことは明確だ。ここでは3点にまとめよう。
第1に、時短が目的化しない働き方改革にしていくことだ。これは文科省もよく認識しているのだが、少なくとも、教育委員会や学校の一部には伝わっていない。在校等時間を短くすることが目的ではなく、健康確保のため、あるいはよい人材を獲得するためには、長時間勤務ではマズいのだ、ということを共有したい。
目標、進捗管理の指標としても、残業時間(時間外の在校等時間)だけでなく、教職員の健康やウェルビーイングを示す指標を含めるべきだと思う。
例えば、ストレスチェック結果、精神疾患による休暇・休職者数、ワーク・エンゲージメントなど。私が数年前に全国の都道府県・政令市の働き方改革に関わるプランについて網羅的に調査したところ(『先生を、死なせない。教師の過労死を繰り返さないために、今、できること』)、こうした多面的な目標設定と進捗管理をしている自治体はごく少数で(例外的だったのは愛媛県や長野県)、ほとんどの自治体が在校等時間の削減をメインもしくは唯一の指標としていた。
保護者などにも働き方改革の趣旨をしっかり伝えることはとても重要だ。深刻な睡眠不足ぎみの教員も多いのだが、そんな状況では、授業や子どもたちへのケアにとってもよいわけがない。
私が校長向けの研修会でよく申し上げているのは、入学式のあとの児童生徒と保護者向けのガイダンスで、長時間勤務を見直す理由を話したほうがよいということ。「校長の仕事としましては、児童生徒の安全を守ることはもちろんですが、教職員の命、健康を守ることもあります」と言えばよい。
第2に、クラウドツールなども活用しつつ、校外でもセキュアな環境でテレワークできる環境を整えて、その従事時間もモニタリングする。企業などでは、従業員が申告する出退勤状況やタイムカード等のデータと、PCのログを見比べて、乖離が大きい場合には調査や指導に入るところもあるようだ。教育委員会の多くは、出退勤の記録を出せ、と学校に言うだけで、教職員の健康確保に本腰を入れているようには見えない。
第3に、残業が多い人や学校にはそれなりの理由があるわけだから、校長ならびに教育委員会は、背景・要因を探って、対策を講じたり、コーチングを進めたりすることが重要だ。「あなた、今月も45時間超で長いですよ」などと数字だけを見て、叱りつける校長などは、子どもたちにも、テストの点数だけでそういう指導をしてきたのだろうか。
私はいくつかの自治体と組んで学校向けの伴走支援を実施しているが、次の図のようにワークログ(仕事の記録)をとってもらって、振り返りをすることが多い。面倒ではあるが、1週間くらい、どんな仕事にどのくらいの時間がかかっていたか、また、そのときの主観的な幸福感(ウェルビーイング指標と呼んでいる)を記録して、集計結果(例:1週間のうち事務作業に何%、授業準備に何%など)やほかの教職員のログなども見比べながら、自分の仕事の仕方の癖や組織的な問題について考える。
ポイントは個人で改善できることだけでなく、学校(学年や校務分掌など)でできることも検討することだ。忙しいのは、個人の意識や段取りのせいばかりではない。家計簿をつけることに似ているが、単に時短圧をかけるのではなく、実態を見て、改善策を考えることができる。
以上の3点は、一部予算や手間がかかることも含まれているが、多大なコストがかかることではない。文科省はもちろん、各教育委員会でも、いまのままで本当によい方向にいっているのか、何が本当に必要なのか、考えてほしい。
(注記のない写真:C-geo / PIXTA)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




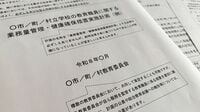





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら