
なぜ、こんなことが起こるのか。ひとつは、回答者数の違いによるもの。もう1つは、道教組(北海道教職員組合「2024北教組9月勤務実態記録」)によると、以下のとおりだ。
つまり、教育委員会把握のデータの中には、休憩時間をつぶして従事している業務や打刻後の業務が把握されていないケースがあって、過少な数字となっている可能性が高い。この問題は、北海道に限らず、各地で起きている問題でもある(いくつかの教職員組合などが報告している)。
なお、文科省の見解としては、本来、自宅で持ち帰って仕事をするのは情報管理や健康管理上問題があるので、原則認められない。よって、在校等時間のモニタリングに、持ち帰り仕事時間はカウントされないようにしている。
ただし、自治体が認めたセキュアな環境でのテレワークは在校等時間に含める、ということを文科省も明言している。コロナ禍の経験もあったし、育児・介護を抱える教職員も多くなっている中、テレワークできる環境を進めることは、まっとうなことだ。
だが、そうした環境整備を進めている教育委員会はまだまだ少数だし、テレワークは夏期休業中に限るなどとしているところもある。文科省調査によると、「教職員が校務用の端末を学校外において使用できるクラウド環境を整えていますか」について「整えていない」自治体は77.3%、「クラウド環境を学校外で使用した際の適切な勤怠管理・勤務時間管理の仕組みを整えていますか」について「整えていない」自治体は90.3%に上る(「GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト~学校・学校設置者の自己点検結果~【速報値】」令和6年12月26日)。
教員の身からしても「そろそろ帰りましょう」とか「教育委員会から指導が来ています」、「優先順位を考えましょう」などとやかましく言われるのも嫌なので、授業準備や事務作業の一部を持ち帰り残業している人は少なくないが、校長も、教育委員会もだれも、その状況を把握していない。これでは健康管理上もかえってマイナスである。
そんな状況下で、財務省からのプレッシャーが強まる中(地方自治体レベルでも似たことが起きていて、予算を握る財政当局からの圧は強い)、文科省としては、現実よりも少なく出ているかもしれないものであっても、教育委員会が把握しているデータを使って、「ほら、働き方改革は進捗していますよ」と言いたくなるのだろう。
言葉は悪いかもしれないが、国をあげての「粉飾決算」のような状況になるのではないか。
関連して、文科省は2016年と2022年に大規模な教員勤務実態調査を行った。これは、30分ごとに主にどんな業務に従事していたか1週間記録するもので、とても精緻な記録だ。持ち帰り仕事についても調査している。調査に協力する教員にとっても、実施する文科省にとってもコスト、労力のかかる調査だが、今後は実施する予定はないという(中教審特別部会で妹尾が質問したことへの文科省の回答、2025年1月24日)。
文科省としては、各教育委員会がタイムカードやICカードで在校等時間の記録を収集しているので、国がわざわざ手間のかかる調査をやらなくていいとのこと。だが、その教委の持っているデータでは不正確なところがあるとしたら、正確な実態把握とはならない。また、どんな業務に時間を要しているのか、多忙の内訳を把握、分析できなくて、どうして有効な対策が立てられるのだろうか。文科省の認識は甘いのか、それとも、承知のうえで意図的に教委のデータを使おうとしているのか。

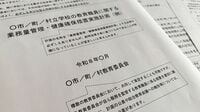





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら