
1980年以降、多くの発展途上国がグローバル経済に統合されてきた。ラテンアメリカ、東アジア、南アジア、サハラ以南のアフリカ諸国は、80年代から90年代にかけて貿易改革を実施し経済成長が加速。途上国と先進国との格差が縮小し始めた。しかし、一連の貿易改革の利益は途上国間で均等に分配されず、経済的な勝者と敗者を生み出した。
貿易理論によれば、貿易自由化は、労働集約型生産に比較優位を持つ途上国の低賃金労働者(生産要素)に利益をもたらすとされている。だが実証研究によると、途上国の労働市場の硬直性が、雇用の流動性を妨げ、貿易自由化はむしろ経済的不平等を悪化させた。80〜90年代の貿易自由化の波は、途上国の低賃金労働者に負の分配的結果をもたらしたのである。
本稿では、このような意図せぬ経済的ショックが途上国の人々の政治的行動にどのような影響を与え、またそれは政治情勢にどのような意味を持つのかについて考えてみたい。

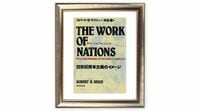






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら