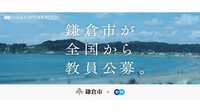「教員不足の問題についてかなり勉強しましたが、法律や歴史的な側面も含めた根本的な理解を土台に議論をしている人は意外に少ない。課題の背景を踏まえたうえで現場のニーズを徹底的に反映した求人サイトを提供できれば、教員不足を解消できるのではと考えました」
背景に「自治体の思い込み」や「不透明な待遇条件」
教員不足の問題は私立校と公立校では事情が異なり、とくに公立校の講師登録制度に課題があると思ったため、公立校特化型の求人サイトを作ることにしたという。
「公立校は予算主義で参入が厳しい一方、私立校なら決裁権が学校にあるため比較的ビジネスが成立しやすいので、よく周りからは『まず私立校を対象に始めたほうがいい』と助言されました。しかし、ビジネス成立のために妥協するのでは、本来の課題解決にはつながらないと思いました」
では、公立校の講師登録制度には、どのような課題があると感じたのか。
「まず、自治体側の認識として『講師に関心のある人は、必ず講師登録をする』という固定観念がありました。教員採用試験の倍率が高かった時代に講師を担ったのは、その年に教員採用試験に合格できなかった方々がほとんどだったと思います。だから、募集すれば集まるという考えが根付いていたのでしょう。しかし、今は講師に関心があるのに講師登録しない人が多いという事態が起きています」
講師登録をためらう理由としては、「どこの学校で働けるのかわからない」「どのタイミングで働き始めることができるのかわからない」「いきなり常勤講師で働くのは自信がない」という3つの不安があることが、ヒアリングから見えてきたという。
公立校では、基本的に講師の募集は都道府県単位で行われ、どこの市町村に配属されるかは事前にわからない。そのうえ、欠員が出たタイミングで行政側から連絡がくるシステムなので、講師登録をしてもいつから働けるのかまったく読めないのだ。また、検討材料が提示されないという問題も大きいという。
「例えば、『数年後に常勤に戻りたいから、まずは非常勤講師として復帰したい』という子育て中の女性は多いのですが、そういう方々は自宅から通える学校なのか、拘束時間はどれくらいなのかといった条件を重視します。驚くことに、これまで自治体は、基本的にそうした待遇条件を事前に提示してこなかったのです。また、教員免許も経験もある登録者には頻繁に連絡がくるようで、断ることが精神的にきついと敬遠する人も多い。ならばほかの業界に行こうと思ってしまうのも無理はないです」
2カ月弱で300名が登録、教員免許保有者が9割
こうした一連のハードルを踏まえて開発されたのが、「ミツカルセンセイ」というわけだ。行政と求職者の情報の非対称性を解消した点が大きな特徴となっている。

求職者はミツカルセンセイに簡単なプロフィールを登録すると、公立校ごとに求人情報の有無や詳しい待遇条件をチェックできる。採用期間や勤務時間、雇用形態、社会保険など福利厚生、経験年数による常勤講師の給与相場、自治体の働き方改革の取り組み、先輩教員の声などをできる限り掲載しているという。
また、すぐに自治体に講師登録をする必要がない点も、応募のしやすさにつながっている。
「自治体の講師登録制度では最初に講師登録をする必要がありますが、求人の条件を確認してから応募し、面談を経て採用が決まったタイミングで登録するという流れにしました。これはシンプルなことですが、教育界では画期的なこと。一方、行政側にとっても、地域で教員免許を持っている人たちが可視化できるというメリットがあります」