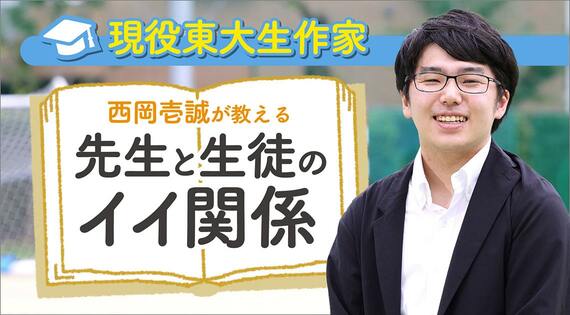「書類も初年度と大きく内容は変えず、とくに面接練習もしなかった」と語る山田さん。
人前で話すことが多く、自身の研究については自分がいちばん知っている、その自信を武器に教授5人を相手にした面接も乗り切りました。
面接中、教授に「何を聞かれても立て板に水が流れるようにスラスラ答えられるのは、それくらい自分のことを見つめて将来のことについて考えているからだよ」と言われたことが今でも印象に残り、大学でも自分らしく研究を続けられる秘訣だそうです。
薬学部を志望した理由は、もともと医療医学分野に関心を持つ中で「薬学を通じて世界全体の底上げがしたい」と感じるようになり、もともと有機化学が好きであったことも高じて薬学部を志望するように。
医学部とも迷ったそうなのですが、「薬を一度生み出したら目の前の患者だけではなく、世界中の大勢の患者様たちを救うことができる」ところに強いやりがいを感じて、薬学部を決意したとのこと。東大薬学部はさまざまな研究室の教授たちの仲が非常によく、一年を通じて多くの行事があることも決め手になったんだとか。
「1年次からカニの研究で研究室に所属しているため、学部生のうちに論文として集大成を出したい。さらに大学の授業を通じて、キンチャクガニが持つ謎同様、世の中の難病やいまだ治療法が確立していない分野に関心を持ち、希少疾患や難病について研究を進めていこうと考えています」と語る山田さん。
薬を作るのみならず、しっかりとそれが人々に届くまでのアプローチや流通システムも整えながら、社会全体に影響を与えていくのが夢だと教えてくれました。
東大に推薦で入ってからの現在は、推薦生同士のコミュニティーやコネクションを活用してさまざまな外部団体で活動したり、研究室に行ったり、サークルにバイトにと充実した日々を過ごしていると言います。
テレビ番組でキンチャクガニの特集を見た友達の声かけがきっかけとなって研究を始めた山田さん。いろんなものに探究心を持って臨む姿勢は広く評価される時代になっているのだと考察できますね。
(注記のない写真:テラ / PIXTA)
執筆:西岡壱誠
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら