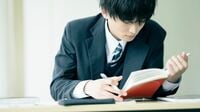北海道平取高校が独自科目「アイヌ文化」を開始、真の「多様性と共生」とは アイヌ文化の伝承者に言語、工芸、歴史を学ぶ
「地域に根差した学びで、生徒たちには多様性や共生について考えてほしい。アイヌに対しても、過去には理解が不足していた時代があり、それは今も課題です。この国の先住民族について知ることには大きな意味があるでしょう。アイヌ文化を理解することは、そのほかのマイノリティーや社会的弱者への理解をも深める相乗効果を生むと思います。みんなが共生できる社会はどんなものか、その実現のために自分は何ができるか、そういったことを考えられる人になってほしいのです」
目標は「アイヌ文化といえば」と言われる高校になること
独自科目の設置には、時流の追い風も大きく影響した。北海道を舞台にした漫画『ゴールデンカムイ』(野田サトル/集英社)が大ヒットし、アニメや映画にもなった。また2020年には、国立アイヌ民族博物館などを含むウポポイ(民族共生象徴空間)が白老町にオープンした。アイヌのことがメディアで取り上げられる機会も多くなり、関心を持つ人は確実に増えている。
鈴木氏も、受験生への説明会で全国を回っていると、「漫画がきっかけでアイヌ文化を学びたいと思うようになった」などと話す中学生に出会うそうだ。だが、初年度の生徒募集は千客万来とは運んでいない。取材時点では入学者数は確定していなかったが、鈴木氏はその感触をこう語った。
「今年も道外からの応募があり、健闘はしていると思いますが――率直なところ、大盛況とまではいえません。とはいえ、全国の高校の例を見ても、1年目からそううまくいくものではないことは覚悟している。こちらも腰を据えて、来年度以降の受験生にもしっかりアピールを続けていくつもりです」
具体的な動きはこれからだが、高校卒業後の進路にも「アイヌ文化」の授業の特色を生かしていきたいと語る。
「アイヌの研究ができる大学といえば、道内では北海道大学と札幌大学が挙げられます。ゆくゆくはこうした大学からも講師を招くなど、高大連携も図っていけたらと考えています」
さらなる野望は、自ら挙げた「アイヌの研究ができる大学」と肩を並べることだ。
「全国的にも、『アイヌの研究ができる高校といえば平取高校』と言ってもらえるようになりたい。そしてアイヌ文化の学びから、日本によりよいコミュニティを作る人を育てていきたい。小さな学校ですが、私たちは大きな夢を抱いています」
(文:鈴木絢子、注記のない写真:denkei / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら