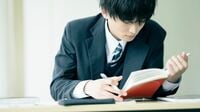北海道平取高校が独自科目「アイヌ文化」を開始、真の「多様性と共生」とは アイヌ文化の伝承者に言語、工芸、歴史を学ぶ

地域の豊かな教育資源を生かし、「点」から体系的な学びへ
この4月から学校設定科目「アイヌ文化」を導入し、道外からの新入生を受け入れる北海道平取高校。学校長を務める鈴木浩氏に、新科目開始までの経緯を聞いた。
「平取町はアイヌ文化の拠点のひとつである地です。これまでも地域の小中学校や高校では、アイヌ文化の伝承者を外部講師に招いた体験授業を行ってきました」
アイヌ文化の残るエリアは北海道各地にあり、道外も含め、その文化や歴史について学ぶことができる高校はほかにもある。だが平取高校では、3年間かけてじっくり理解を深めることが特徴だ。
「アイヌの文様の刺繍を習ったり言葉を教わったりという従来の体験にも、子どもたちは積極的に取り組んできました。楽しいとの声が多く好評を博してもいましたが、それはあくまで単発的な『点』でした。私たちは高校生という年齢を対象とすることもあり、より長期的で系統的な学びが構築できると考えました。アイヌ文化の学習を、点から線、面へと、さらに発展した学校設定科目にすることにしたのです」
教員らや道教育委員会、平取町とも話し合い、方向性を固めた鈴木氏。その後は自ら地域の伝承者を訪ね、高校での教育において、これまで以上の協力を得たいと願い出た。
「伝承者の皆さんにも、先住民族への理解を深めるのはいい取り組みだと言っていただきました。平取町にはアイヌ語に堪能だったり、木工や刺繍の第一人者であったりと、講師を務めてくださる方が多くいる。これは本校ならではの強みだと考えています」
学校で新たな取り組みが検討される際には、多忙な教員のリソースをどう確保するかという懸念が生まれる。だが前述のとおり、この「アイヌ文化」はゼロからスタートするものではない。伝承者も多く暮らしているほか、町にはアイヌ博物館や資料館もあり、人的にも施設面でも教育資源は豊富だった。
従来の学びを地域の力で深化させるのは、高校の魅力化・特色化の取り組みとして理想的だといえるだろう。同校ではカリキュラムの構想時点から地域や外部学識者の意見を聞きつつ、校内研修も実施し、地域一丸となって内容を練ってきた。
授業は週に1度、年間で35時間のいわゆる「1単位」で行う。1年生では言語を学び、アイヌの考え方についての理解を深める。2年生では木工や刺繍などの工芸を体験し、3年生では近現代に至るまでのアイヌの歴史や精神世界などについて学習する予定だ。