国立市が東大とタッグ、「フルインクルーシブ教育」に本気で動き始めた背景 原則「すべての子どもが同じ場で学ぶ」を目指す
小国喜弘氏(以下、小国) ユネスコの「Global Education Monitoring Report 2020」では、「インクルーシブ教育の恩恵について議論することは、奴隷制度やアパルトヘイトの廃止の利益について議論することと同等である」と述べられています。奴隷制度やアパルトヘイトに関する議論は「廃止すべきかどうか」という話ではなく、人間の権利の話ですよね。それはインクルーシブ教育も同じ。「障害のあるなしで学びの場を分ける隔離教育は、隔離された社会の入り口になる」というのが国連の考え方です。
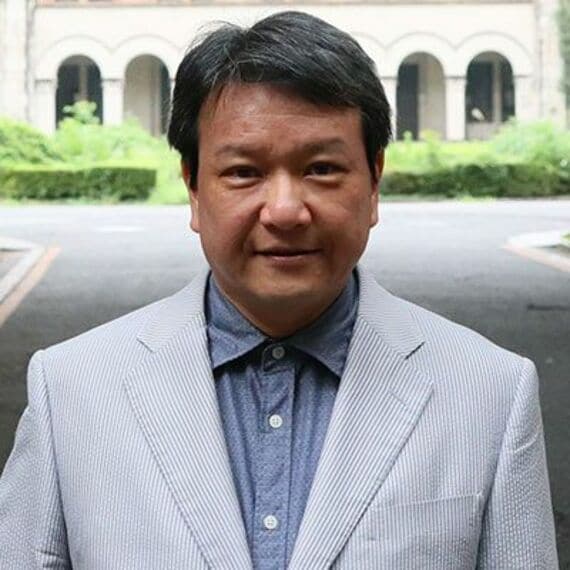
(写真:小国氏提供)
そのため国連は2022年9月、日本政府にインクルーシブ教育の改善を求める勧告を出しました。これは特別支援教育をやめなさいということではなく、「通常の学級でできることを増やしましょう」ということ。国立市が目指す教育も、ソーシャルインクルージョンを前提に構想されたものであり、国連の問題意識と同じ文脈にあるといえるでしょう。
ちなみに米国をはじめ諸外国でも、教育分野は隔離が制度化されやすいこともあり、特別支援学校や特別支援学級の教育には「フル」という言葉を用いず、地域の普通学校・普通学級で学びが保障される教育には「フルインクルージョン」という言葉が使われています。
──フルインクルーシブ教育の実現に向けたロードマップはありますか。
橋本 まさに今、検討中です。年度内に取りまとめて発信できればとは思いますが、教育長が「時限を設けず十分に議論を尽くすこと」と明言しているように、丁寧な議論を優先します。ただ、計画ありきで動くのではなく、合意形成できた部分から予算を申請するなど、柔軟に取り組んでいく考えです。
──現時点で、具体的にどのような取り組みが必要だとお考えですか。
荒西 現在も支援員の数は多いですが、改めて必要な人員体制の整備を検討します。教員の意識改革も必要だと考えており、今年は市民と意見交換をする「国立市のフルインクルーシブ教育を語る会」の教員バージョンを開催したほか、全教員を対象に「子どもの多様性に即した支援のための研修」を実施しました。今後はモデル校の設定なども予定しています。
ただ、教員からは「時間的・心理的余裕がない現状で不安だ」という声もあり、時間や心の余裕の創出も課題です。また、保護者や地域の理解も必要なので、引き続き対話を重ねていきます。
学校現場ではすでに、特別支援学級で学んでいた子が通常学級で勉強する機会が増えるなど、現場の判断でフルインクルーシブな環境を整える事例がたくさんあります。そうした柔軟な個別対応を市は引き続き応援するとともに、すべての学校で当たり前に実施できるよう情報共有もしていきたいです。また本市は、幼児教育における発達支援にも力を入れていますので、うまく連携して切れ目のない個別支援も実現したいと思います。
「通常学級での差別や排除をなくす挑戦」でもある
──特別支援教育を受けている児童生徒の保護者からはどのような反応がありますか。
荒西 「個別支援はなくさないで」「特別支援学級がなくなるのが不安」という声もあり、一足飛びに推進することは適切ではないと考えています。個別支援が必要であることやその選択は尊重しつつ、通常学級の指導を充実させることで、特別支援学級を選ばなくてもいい状況をつくっていきたいです。
──小国教授はどのような形で関わっていくご予定ですか。
小国 市の仕組みの整備と、足元の課題への対応という2つの側面から、知見を提供するほか、東大の研究者と国立市をつなげていきます。また、私がセンター長を務めるバリアフリー教育開発研究センターは、大阪府吹田市やDPI日本会議(障害者当事者団体)とも連携協定を結んでいます。そうしたつながりも活用して当事者の方々と緊密に連携を取りながら、国立市での好事例をほかの自治体に横展開し、日本の学校教育がフルインクルーシブな形へと転換していくお手伝いができたらと考えています。






























