日本の女子大初、注目の「奈良女子大学工学部」開設2年目の手応えと課題 女子を引きつけた「人と社会のため」という視点
「工学部の女性の3割は、大学時代に男性主体の環境で苦労した経験から、男性社会である工学系の就職先を選ばないそうです。ある企業の執行役員の方は、そのことに危機意識を持っており、女性エンジニアのサポートが今後の課題だと協力を申し出てくれました。マイクロンが本学のコーチングプログラムに賛同してくれたのも、男性中心の社会に出ていくうえで、女性のメンタルトレーニングの支援が重要だと認識しているからです」
企業が協力的なのは、AIが工学に関与する時代になったことも大きいという。
「男性だけで開発すれば、どうしても男性向けのプログラムになってしまいます。実際、そのために大手IT企業は初期に失敗してきました。女性進出やダイバーシティーは決してきれい事ではなく、産業の発展に必要だから推進されているのであり、米国ではすでにダイバーシティーへの取り組みが投資基準になっています。先端的な企業ほど、女性エンジニアの育成に積極的だと感じます」
主体性を育み、やりたいことをどこまでも追求できる社会へ
工学部1学年の学生数は、1期生、2期生とも48名。5割は近畿圏からの進学者だが、それ以外は全国から集まってきている。3年生の段階で編入生が10人前後入学するため、卒業時には60人前後となる予定だ。一般入試の倍率は2022年度が6.3倍、23年度は2.7倍となった。
「当初、『理系女子高生の主な進路先は看護と薬学で、工学部は人気がない』と高校の進路担当の先生に何度も言われましたが、想定以上にニーズがありました。入学した子たちに聞いてみると、『人と社会のための工学』という本学の考え方に賛同してくれた子が多かったと感じています」
設立から2年目になるが、実際、女性のモチベーションはやはり「人や社会のため」という点にあると藤田氏は日々感じている。工学に向き合う際、男性はいかに効率化してパワーを発揮するかという性能や技術的な部分を重視する傾向にあるが、工学部の女子学生を見ていると、困っている人がいるから助けたいというところから発想して工学で課題を解決しようとするアプローチが非常に多いという。
「そうした守る・育てるという発想は、まさにSDGs(持続可能な開発目標)の時代に求められていること。社会の目標が、いわゆる『開発』から『持続可能性』に変わったこと、いわば21世紀型の工学が求められるようになったことが、私も授業を通じて実感として理解できるようになりました」
また半年に一度、教員2名対学生1名でコーチングを行っているが、「おとなしい印象だった子が別人のようにパワフルに話をするようになるなど、いい方向に変わってきているなと思うことが多いですね」と藤田氏。女子学生が伸び伸びと成長できるのは、女子大ならではの環境も大きいようだ。
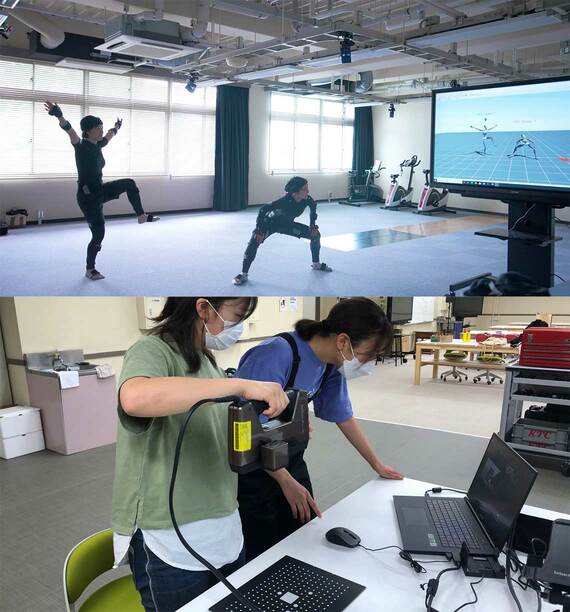
「共学の工学部では例えば50人だと、女性は2~3人くらいしかいません。教授陣の女性比率も低く、圧倒的な男性社会ですから、女性の発想や必要なサポートもないがしろにされがちです。だからコーチングのようなサポートも共学の工学部にはありません。女子大は、男性の目や意見を気にせず、女性が人間らしく活動して学ぶにはいい環境だと私は信じています」






























