国家の存亡より「財政黒字」を優先する思考回路 財務省で伝承されてきた「財政規律の大原則」
実際、日本の財政赤字は、1980年代後半に縮小し、プライマリー・バランス(基礎的財政収支)は1987年度に黒字化し、1991年には8.8兆円の黒字を達成した。しかし、その裏側で、民間部門は、バブル景気に沸き立って、借金を重ねていた。したがって、バブルが崩壊すると、民間部門は債務を縮小させ始め、それに伴って財政赤字が拡大していった。
同様に、アメリカでも、1990年代後半に財政赤字が縮小し、1998年度には財政黒字を計上したことがあったが、その裏側では、いわゆるITバブルが発生していたのである。
このように、財政黒字は、その裏側でバブルが発生している可能性を示す兆候と考えるべきである。しかし、バブルは長くは続かないのだから、財政黒字が当たり前のことになるはずがない。しかも、財政黒字がバブルの発生の裏返しであるならば、それは、政府が目指すべきものでもない。
齋藤氏は、財政の黒字化を目指して増税を求めてきたと証言している。しかし、増税が景気の悪化を招けば、民間部門はかえって債務を削減しようとするから、その裏返しで、財政赤字はさらに増えることになる。しがたって、増税しても、財政の黒字化は不可能であり、むしろ逆に財政赤字を拡大する可能性すらある。
国破れて黒字あり
では、民間部門の大幅な赤字(バブルの発生)を回避しつつ、財政黒字を当たり前のことにするには、どうすればよいのであろうか。
「『政府部門』の収支の黒字=『民間部門と海外部門』の収支の赤字」なのであるから、海外部門の収支の赤字(経常収支黒字)を大幅に計上するしかない。
しかし、日本のような内需の占める割合が大きい大国で、財政黒字が当たり前になるほど巨額の経常収支黒字を計上し続けることは、不可能である。実際、財政黒字が恒常化している国の多くは、内需の小さい資源輸出大国である。つまり、経済構造が日本と正反対の国々だ。
仮に、経常収支黒字を目指すのだとしても、経常収支は、海外経済の景気動向に大きく左右されるため、政府がコントロールできるものでもない。
例えば、世界経済が不況になれば、経常収支の黒字幅は縮小せざるをえないだろう。それでも、経常収支の黒字化を目指して輸出を拡大しようとしたら、それはいわゆる「近隣窮乏化政策」であり、禁じ手である。
したがって、「財政の黒字化は当たり前のことでなければならない」などという「財政規律の大原則」は、原理的に達成できないというだけではなく、達成するのは望ましくないという代物なのである。
それは、「『政府部門の収支』+『民間部門の収支』+『海外部門の収支』=0」であることを考えれば、当然である。
齋藤氏の証言によれば、財務省は、そんなことも知らずに、「財政の黒字化は当たり前のことでなければならない」と固く信じ込み、それを組織として脈々と受け継ぎ、政治に対して増税を求めてきたということになる。
それでは、「国が滅びても、財政規律が保たれてさえいれば、満足」だと批判されても、仕方あるまい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

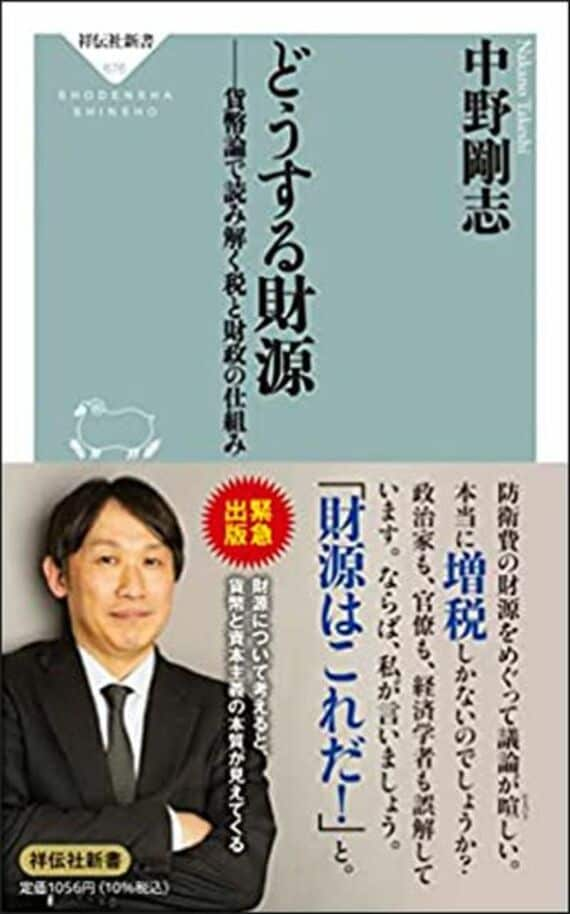






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら