外国にルーツを持つ子どもが過半数の時代も…横浜の市立小学校での実践 少人数指導や取り出し授業は日本人にも利点が
「飯田北いちょう小では、多文化共生の地域・学校づくりのためにさまざまな方と協働してきました。学級担任はもちろんのこと、養護教諭や栄養職員、用務員、自治体や地域ボランティアなど、学校がある地域のすべての方々と共に取り組んだのです」
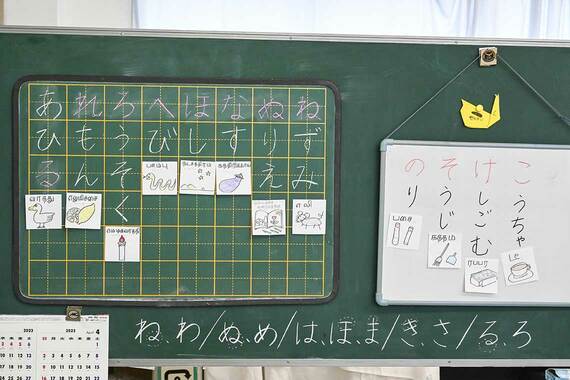
教室で「お客さん扱い」されるマイノリティーの子ども
恵まれているとされる環境では、思いがけない弊害もあるという。
「教員は通常業務だけでも忙しいので、国際教室担当の教員が多いほうがいいというのもとてもよくわかります。ただこれは私見ですが、専門の担当教員が多いと、学級担任との温度差も生じうるのではないでしょうか。子どもが学校でいちばん多くの時間を過ごすのは自分の教室です。学級担任が『国際教室の担当に任せればいい』と考えてしまうと、子どもにとって教室での時間がつらいものになりかねません」
例えば現在菊池氏がいる同市立上飯田小学校は、飯田北いちょう小と1キロ程度しか離れていないにもかかわらず、外国にルーツを持つ子どもの割合は全体の7%にすぎない。こうした学校では、彼らはいわば「お客さん状態」で扱われることがあると菊池氏は語る。菊池氏は、自身が過去に見たその例を挙げた。
「国語の授業で、句点で区切って子ども一人ひとりに音読をさせることがありますよね。そのとき教室には来日したばかりの子どもがいましたが、日本語がわからないことに配慮したのか、教員はその子を飛ばして授業を進めていました。そのほかにも、日直など当番制で回ってくるものはすべて同じ扱いをしていたと聞きました」
前述のとおり、子どもはほかの子どもを非常によく見ている。日本人の子どもにとっても、外国にルーツを持つ子どもが困っている場面は成長のチャンスなのだ。だが教員が「その子はお客さん扱いしていい」という慣習を作ってしまえば、すべてはそこで終わってしまう。菊池氏も「長くやっている専門教員がいなかったり、加配教員がいなかったりする学校でこそ、どう工夫して子どもを支援していくかが重要だと考えています」と語る。次回は、こうした「外国にルーツを持つ子どもがマイノリティーになる学校」での実例や課題を掘り下げる。
(文:鈴木絢子、撮影:大澤誠)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























