
宿題が原因で親子げんかになってしまう…
今回のテーマは宿題です。この記事を書こうと思ったきっかけは、ある小学1年生の保護者の方の話を聞いたことからでした。そのお子さんは、漢字の書き取りがあまり好きではなく、入学当初、家庭で宿題をさせるのも一苦労だったそうです。なぜ嫌なのかを聞いたところ、「きれいに書けていないと昼休みに書き直しをしなくてはならず、お友達と遊べないから」と。
お母さんは、子どもの気持ちに共感しつつ、それでも宿題はさせなくてはならないため「その子の夢である飼育員さんになるためには、字をきれいに書けるとどんないいことがあるか」を一緒に考え、「看板の文字がきれいに書けていないとお客さんが読めない」と子どもが気づいて、書き取りの宿題もするようになってホッとしたと話してくれました。
宿題をする意味から考えさせるこのお母さんのアプローチはすばらしいなと感心していたのですが、2学期になり事情が変わっていました。
毎日同じように出される書き取りや計算の宿題が、家庭の中で結構なストレスの種になっていたのです。そこで、お母さんが先生に相談したところ、「そんなものですよ、宿題って」という回答だったそうです。
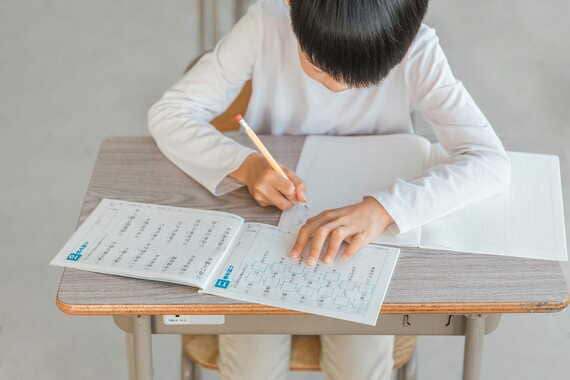
(写真:buritora / PIXTA)
でも本来は学ぶって楽しいことのはず。「このままでは子どもが勉強は楽しくないものだと思ってしまう。それでいいのか。宿題の目的は何なのか」を考えて、先生に相談。漢字を覚えて書けるようになるのが目的なら、やり方は工夫させてもらいたいとお願いして、子どもと相談しながらやり繰りしていると話してくれました。宿題は、子どもにとって楽しくないものになっていてやりたくない。でもやらなければならないものだから、親もどうにかしてやらせようとする。
また、「宿題をするかどうかは子どもの問題だ」と割り切ったとしても、やらないまま行かせたら親の責任になってしまいかねない。やらなくてはならないことをやらないというのもよくないから、子どもと話し合いをしたり、ルールを考えたり、宿題が原因で親子げんかになってしまう。こんな光景は、日本全国の家庭で繰り広げられていることでしょう。
こなすだけになっている宿題は、本当に必要なのか
その試行錯誤にも意味がなくはないけれど、「主体的・対話的・深い学び」が重視され新しい学力が求められる中で、一律に出される宿題は効果があるのだろうか、そもそも宿題を出す意味や目的は何なのか考えてみようと思い、まず宿題の実態を取材することにしました。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表
小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子ども達の笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWeb連載まで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある
(写真:中曽根氏提供)































無料会員登録はこちら
ログインはこちら