立命館小学校・正頭英和「Minecraft」使った授業で英語を話す力が伸びるワケ 豊富な音声コンテンツを使い授業の組み立てを
――ICTの活用が進む中、英語教員や英語教育のあり方も変化しつつあるのですね。
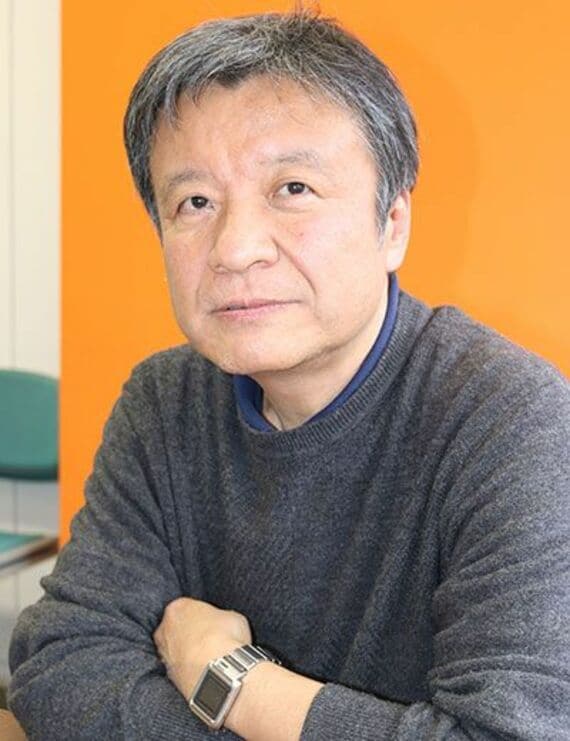
早稲田大学教育総合科学学術院教授
ワールド・ファミリー バイリンガル サイエンス研究所学術アドバイザー
早稲田大学教育学部英語英文学科卒業後、高等学校の英語教員を経て、筑波大学大学院教育研究科教科教育専攻英語教育コースで修士号を取得。短期大学に勤務後、ロンドン大学大学院ユニバーシティ・カレッジで音声学修士、ロンドン大学教育研究科(IOE)を経て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)にて応用言語学博士を取得。その後、オレゴン大学で教鞭を執り、2005年から現職。13年から14年まで、UCLAの客員教授兼研究員。専門は、第二言語習得、外国語の音声習得、英語教育、バイリンガル教育など
(写真:IBS提供)
原田:これまでの英語教員は、例えば英語の発音において「これが正しい発音です」と自分がモデルとして示さなければいけなかったのが、今ではICTが正確な発音を教えてくれますし、英語で書いた文章も、文法的に正しいかどうかをICTが判断し、別の適切な表現の仕方を教えてもらうことができるようになりました。このように「英語の知識を単に子どもたちに伝える」という教員の役割は減っていきます。
むしろ、これからの英語教員は、正頭先生の実践のように、子どもたちが「英語をもっと話したい」「もっと学びたい」と思えるような動機づけを行い、英語による活動のゴールに向かって学習のプロセスを楽しんでいたらいつの間にか英語を学んでいた、というような授業設計ができる先生が必要になるのではないかと思います。
ポール:ICTは日常生活の中にも当たり前に溶け込んでいて、学校で学んだ英語に興味を持ったら、自宅に帰ってスマホやパソコンで調べながら、子どもたち一人ひとりが個人ベースで楽しく学べる時代です。学校はあまり堅苦しくならず、子どもたちが日常的に親しんでいるICTを柔軟に取り入れる姿勢が必要ではないでしょうか。
原田:これまでの日本の英語教育は、学習者が日常生活の中で知りたい知識や情報を自主的に調べる英語学習(インフォーマルラーニング)が欠けていたように思います。多くの英語の授業では、例えば語彙や文法の概念などを受身的に学ぶことが主流でした。しかし、このような概念はたくさん英語に触れながら何となく時間をかけて学んでいくものでもあるんですよね。そのように時間をかけて学ぶ自主的学習を支援するのが、ICTだと思っています。
ポール:ICTを活用し、「インフォーマルラーニング」を充実させながらクラスの友達や先生と力を合わせて海外の子どもたちと異文化交流するなど、授業を通じて人と人とのつながりを深めていくようなやり取りが、ICTを通して実現できる取り組みだと思います。
(注記のない写真:正頭氏提供)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら