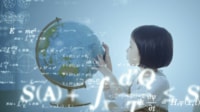1989年から「情報教育」、神大附属中高「問題解決のためのICT活用と表現」の今 1人1台端末の目的は「生徒自身による学習管理」

フロッピーディスクの時代、1989年から「ICT教育」を開始
1984年、中高一貫教育の男子校として開校した神奈川大学附属中・高等学校。当時は、厳しい受験指導や詰め込み教育が問題視される時代だった。そうした中で初代校長の大澤清克氏は、グローバルな視野を養う教育の必要性を感じ、「情報教育」「理数系教育」「英語教育」の3本を柱とする構想を打ち立てたという。その情報教育を託されたのが、87年に入職した小林道夫氏だ。

神奈川大学附属中・高等学校 副校長
1963年生まれ。東京学芸大学教育学部卒業、関西大学大学院博士課程後期課程単位修得後退学。情報学専攻。87年神奈川大学附属中・高等学校専任教員として情報教育を担当。プログラミング教育、デジタルデザイン、インターネットを活用した海外との交流学習などの実践を重ね、2000年より中学校技術科、高等学校情報科教科書執筆。03年よりNHK高校講座「情報A」「社会と情報」番組講師担当。13年に未来の夢の乗り物である宇宙エレベーターをテーマとしたロボット大会「宇宙エレベーターロボット競技会」を発足し実行委員長を務める。18年より現職。主な著書に『ITと教育』(御茶の水書房)、『情報教育と国際理解』(日本文教出版)など
その頃はICT教育を行っている学校がまだまだ少なく、小林氏は、先行して情報教育に力を入れていた国立大の付属高校や研究会などを訪ね、勉強を重ねたという。そして89年に約50台のパソコンを配したコンピューター教室が設置され、同校のICT教育がスタート。小林氏は次のように振り返る。
「タイピングや表計算、プログラミングを中心とした授業を展開していましたが、当時はフロッピーディスクで起動やデータ保存を行っていた時代。転機となったのは、パソコンをリプレースした頃です」