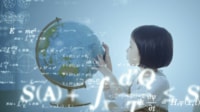1989年から「情報教育」、神大附属中高「問題解決のためのICT活用と表現」の今 1人1台端末の目的は「生徒自身による学習管理」
小林氏は、教員の負担と不安を減らすため、校内に専門の職員が常駐するICTサポートセンターをつくった。生徒と教員の情報端末は計1400台以上あるので、機器の管理やトラブル対応、アプリのアップデートなどの問題はすべてこのセンターが対応している。
また、MicrosoftのOfficeや授業支援クラウドシステムのロイロノート、学習管理システムのClassi、オンライン学習サービスのスタディサプリなど、基本ツールの授業活用の研修は頻繁に開催。「とくに生徒の1人1台端末の導入を始めた2018年からの3年間は年間5~8回ほど研修を行いましたが、教員全体のリテラシーが上がりました」と、小林氏。ただ、「ここまでは最低限できてほしい」というレベルを高くしすぎないよう注意した。
さらに「自由度を設けることも大切」だと小林氏は言う。教科により特性が異なり、教員によっても教え方は違うため、教員が自身で最適なものを選べるようアプリも豊富に用意したという。
22年春から高校で「情報Ⅰ」の授業が始まり、25年には大学入学共通テストの出題科目に「情報」が加わる予定だ。
「『情報Ⅰ』は本校でもすべての要素を網羅する形で教えていますが、おそらく入試で出される問題はもっと難しくなるはず。座学だけで理解することは難しく、とくに実際にプログラミングをしてみたり、ポスター作りなどのデザインを経験したりしないと解けない問題が出るのではないかと思っています。今後は授業を行ったうえで、本格的な対策を考える必要があると感じています」
しかし、同校は約30年前からクリエーティブツールを多数導入しており、創作実習にはアドバンテージがあるといえるだろう。行事や生徒会選挙でポスターやWebサイトを作ったり、学園祭ではプロジェクションマッピングを作って披露したりと、使いこなす生徒も少なくない。
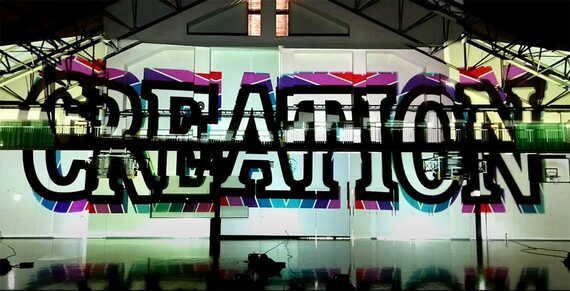
生徒のクリエーティブ能力をさらに高めるために、22年度からは生徒の1人1台端末にAdobeのCreative Cloudを導入している。長年ICT教育に取り組んできた小林氏は、次のように強調する。
「何をするにもICTを使って表現できるかどうかで、やれることは大きく変わります。これは今後の話ではありません。今すでにもう、ICTを確実に扱うスキルと問題解決力を身に付けることは必須の時代になっているのです」
(文:酒井明子、写真:神奈川大学附属中・高等学校提供)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら