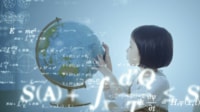1989年から「情報教育」、神大附属中高「問題解決のためのICT活用と表現」の今 1人1台端末の目的は「生徒自身による学習管理」
また、生徒たちはICTツールを学びの武器にできただけでなく、教員を頼らなくなったという。1人1台端末の導入に当たって、教員にも生徒たちにも「目的は生徒自身が自律し、学習管理を行えるようにするため」という考えを事前にしっかりと共有したというが、「実際、何事も自分たちで進んで解決するようになりましたね。グループミーティングをはじめ研究の進め方も上手になったと思います」と小林氏は言う。
教材や連絡事項だけでなく、自身の成績データ、大学入試の情報や過去問データ、大学説明会の動画までクラウド経由でアクセスできるようにしたことで、生徒は必要な情報を必要なときに自ら取りにいけるし、学習の管理や振り返りも自分でできるようになった。質問も、校内で先生をわざわざ探さなくてもタブレット端末を介してすぐできる。
「逆に『先生がいないからできません』『宿題は聞いていません』と言えないんです。まだ検証はできていませんが、事前に教材配信や計画の伝達を行うことで、生徒たちはやるべきことが明確になり、自ら動けるようになっていると感じます。人に言われてやるより、自分で考えて行動するほうが楽しいですしね。また、限られた時間を上手に使ってスケジューリングできるようになったことが、学力向上にもつながっていると思います」
21年度の卒業生219人のうち、国立大学の現役合格者は65人と、前年度の47人から大きく伸長。そのうち3人は東京大学に合格した。小林氏は次のように分析する。
「進学実績は毎年異なるものですが、テストや成績がデータとして可視化されていつでも確認できるようになったため、しっかり勉強をしなければという意識は以前より強くなったと思います。また、宇宙エレベーターロボットなどICT教育に力を入れている点に引かれて入学してくる子も多く、ここ数年は理系希望者が増加傾向にあります」
ICT活用を広げ「働き方改革」にもつなげるため必要なことは?
ICT活用は、教員の働き方改革にも寄与している。現在、会議では紙は配らずに資料は共有サーバーに上げており、議事録もMicrosoftのデジタルノートアプリ「OneNote」でまとめている。
「これにより100人以上いる教員の情報共有がスムーズになりました。その分、教員もある程度、授業や指導など生徒と向き合う時間を増やせているようです。また採点アプリも導入しているので、答案をPDF化することで採点や集計が楽になっただけでなく、答案の紛失や改ざん防止などのリスク管理にも役立っています」
しかし、当然ながらパソコン操作を苦手とする教員もおり、当初からスムーズにICT活用がうまくいったわけではないという。
「今、多くの学校がGIGAスクール構想で苦労されていると思いますが、私も最初は何が必要で、それを年度ごとにどう充実化させていけばいいのか、ロードマップを描くことがすごく難しいと感じました。ただ確かなことは、いくら機器が整備されていても、先生が使ってくれなければダメだということ。学校全体で活用を広げるには、先生方の不安を払拭し、理解してもらうことが重要になります」