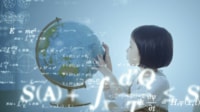1989年から「情報教育」、神大附属中高「問題解決のためのICT活用と表現」の今 1人1台端末の目的は「生徒自身による学習管理」
プログラミングやコーディングの学びに限界を感じ、94年にAppleのMacintoshを導入。これを機に、現在の同校のテーマである「問題解決のためのICT活用と表現」という方向性が見えてきたという。
プログラム機能を持ったカード型プレゼンテーションソフトのHyperCardを使い、グループ活動や課題をまとめて発表するアクティブラーニングに力を入れるほか、AdobeのPhotoshopなど文字ベースではない表現が可能なソフトウェアも取り入れた。「とくに当時はインターネットがなかったため、創造性を育めるツールを選ぶことが非常に大切でした」と、小林氏は言う。
96年にはインターネットの活用を前提とした「情報教育の基本方針」を策定。中・高6年間を通したカリキュラムの実施、Webページの作成と情報発信、コンピューターを表現の道具として創造性の開発と個性の発揮を目指すこと、国内外での共同研究などを基本方針とした。

こうした方針の下、さまざまな活動が広がっていった。例えば98年からは、学習に利用できるWeb作品を日本語と英語で制作するコンテスト「ThinkQuest(現・全国中学高校Webコンテスト)」に毎年応募しており、何度も入賞を果たしている。
2010年からは早くもロボット教育をスタート。チームでセンサーロボットを作りプログラミングを行って競いながら成果発表をする問題解決型学習である。12年からは、宇宙エレベーターロボット研究も始まった。現在、同校では中3になると全員が、宇宙ステーションに人や物資を運ぶ宇宙エレベーターについて学び、地上とステーションを昇降するロボットを作り成果を競う競技会に参加する。

1人1台端末で生徒による「学習管理」が可能に、学力も向上
同校ではコロナ禍前の2018年に、中3全員にタブレット端末のSurface Goを導入。19年には中2〜高1の全員、22年には全生徒の1人1台端末の活用を可能にした。現在、基本的に教材は電子黒板に投影し、生徒はすべての授業でタブレット端末を活用。担任などからの連絡事項の確認、出欠確認、課題の配布や提出、教材配信などは、すべてアプリやクラウドを通して行っている。

中3と高1が2学年合同で行う「探究の時間」における変化を紹介しよう。この時間は、国際問題や宇宙など20以上のテーマの中から、生徒たちが自分の興味のあるゼミを選択し、4~5人のグループで探究活動を行う。中間発表や論文作成のためのリサーチや資料の共有にタブレット端末をフル活用するようになったのはもちろん、コロナ禍ではZoomの活用が一気に進んだという。

「生徒たち自身が研究テーマに合った専門家を探して直接コンタクトを取り、オンラインで話を聞くことができるようになったのです。以前は専門家の話を聞くとなると講演形式でしたので、時間もお金もかかり大変でした。しかし現在は、生徒たち自身が直接大学の研究室や研究機関とつながることができるようになりました」