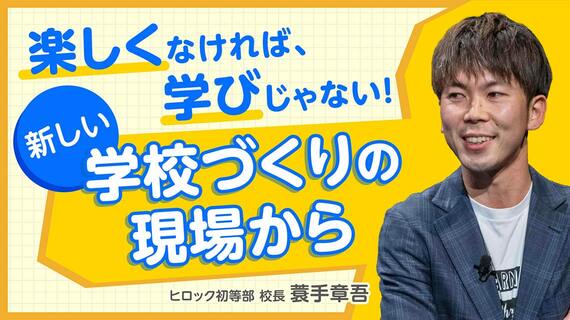公立学校教員を辞した今も、ヒロック初等部という教育現場で自由進度学習を実践しています。そこには高2の数学を学ぶ子の隣で、ひらがなを読む練習をしている子がいます。どちらも互いの存在を感じながら、決してばかにすることなく、同じ仲間として実にさまざまな刺激を相互に与え合っているのです。インクルーシブ教育は夢物語でも何でもなく、現に実現できるのです。
では、みんなが必ず同じ場所で学ばなければいけないのかというと、私はそうは考えていません。その子の成長を第一に考えたとき、普通学校では十分に環境が整えられないこともあるでしょう。だからこそ、冒頭でお話ししたように、インクルーシブ教育は、その子が「自分の学びたい環境で学べる」ことが重要なのです。
特別支援学校に勤務していた頃、多くの保護者の方から「本当は普通学校で学ばせたかった」「おたくは特別支援学校に行ってくれないと困ると言われた」と痛切な声を寄せてくれました。自ら選んできたのではなく、排除されてきたという感覚を持ってしまっている。それって子どもにとっても不幸なことですよね。落ち着きがなかろうが、日本語が苦手だろうが、体が弱かろうが、大人になれば私たちは同じ社会で、支え合いながら生きていくのです。
そして、それが自分の「弱さ」や「苦手」を表出できる、誰しもが安心して暮らせる社会に直結します。そのためには、学齢期という猶予期間の中でこそ、すべての子が多様性について知り、学び、時には失敗しながら深めていく必要があると思っています。
もっと「小さな声」「声なき声」に耳を傾けてみませんか。理想論や夢物語で片付けず、ちょっとした工夫とアイデアで、まさに理想の学び場は実在しているのですから。
(注記のない写真:ペイレスイメージズ1(モデル)/ PIXTA)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら