「吹奏楽文化」があと20年で消える?学校から「部活」切り離す前に考えたいこと 経済格差や地域格差を踏まえた総合的な判断を
───教師や生徒の数が減少している過疎地域についてはいかがでしょうか。
新山王 これまで吹奏楽コンクールのA部門(中学の部は50名以内、高校の部は55名以内の大編成)に出ていたけれど、少子化でアンサンブルコンテスト(3~8名の少人数編成)にしか出られなくなってしまったという学校が多くあります。そういった学校の生徒や先生たちが地域と手を取り合ってやっていくのは大切ですよね。
石津谷 青森県むつ市で活動している「下北Jr.ウインドオーケストラ」は、下北半島の人口減少で各校が吹奏楽部を存続させることが難しくなったために、地域全体で小学生が集まって40名程度で練習しているというよい事例です。海上自衛隊の大湊音楽隊や、一般の市民吹奏楽団など、大人たちが一体となって子どもたちに音楽の醍醐味を教えていて、演奏もとっても上手です。
現在の吹奏楽コンクールの参加規定では、地域で活動している多世代型のバンドは、一般の部での出場になっています※。今後は、例えば小中高で一緒に練習している地域団体は高校の部に出られるようにするなど、団体の多様化に対応した施策にも取り組まなければいけないと考えています。
※吹奏楽コンクールの出場区分は、小学校の部、中学校の部、高校の部、大学の部、職場・一般の部の5区分

教師に手当てを、子どもに豊かな文化経験を
───学校の部活動機能を維持したい一方で、「土日に部活動をするのは嫌」という教員志望者が増えています。
新山王 公立学校の教員には残業代が支払われないため、やりがい搾取になっている側面があることも大きいと思います。教師の熱意ややりがいに甘えて何でもボランタリーに頼るのは、限界がある。教師の兼職兼業制度を整えて、例えば日中は教師として、夕方以降や休日は部活動指導員として従事するなど、正規の労働への対価に加え、それ以外のプラスアルファの働きをちゃんと評価する仕組みが必要です。そのためには、運動部と同じように部活動指導員の養成制度を早急に整える必要があります。
石津谷 教員の働き方改革においては部活動だけを論じるのではなく、本業の負荷をしっかり見直すべきとも思います。文化庁が部活動ガイドラインを公表し、さらにコロナ禍で部活動時間が減少しているにもかかわらず、教員の残業時間は減っていません。部活動をなくせばそれで働き方改革というのはおかしくて、本業そのものの負荷が圧倒的に多くなってしまっている。本業をきっちりこなすだけで残業上限に引っかかり部活動ができないケースもあります。
あとは、子どもを第一に考えられているかどうか。教師の長時間労働はもちろん解消されるべきですが、それ以上に、日本の将来を担う子どもたちに文化活動を通じた成長を提供することに改革の主眼を置くべきだと考えています。長時間労働をなくしたいので翌年から廃部です、今後はお金を払って地域のクラブでやってくださいというのでは、子どもを犠牲にして教員を救うようなことになってしまいかねない。部活動は日本が世界に誇る文化。私も吹奏楽の灯を消さないよう、現場での指導を続けていきたいと思います。
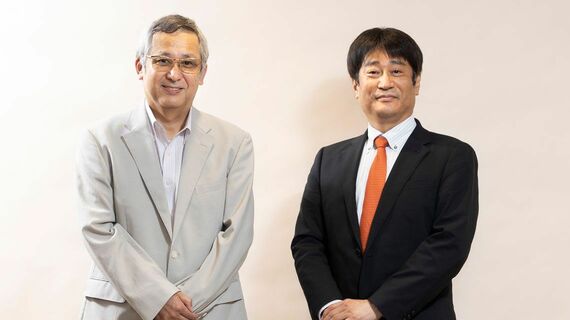
(企画:吉田明日香、文:吉田渓、注記のない写真:m_spike / PIXTA)
関連ページ:体育を「運動が不得意な子」も楽しめる授業にする方法
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























