新学習指導要領の学習評価「3観点」を活用して主体性を育成、脱・証拠探しへ プレッシャーが呼ぶ「えんま帳」「細切れ評価」
情意の評価時に注意すべき点はほかにもあるという。
「教員が子どもの態度を評価することは、単なる好き嫌いの懲罰にもなりかねないリスクをはらんでいます。教員が『えんま帳』をつけるような評価では、子どもも教員自身もつらいはず。子どものウェルビーイングのためにも、教員の働き方のためにも、日常のすべてを評価につなげるのは不可能だし望ましくないと理解しておきましょう」
「形成的・総括的評価」を区別し、学びも評価も変わろう
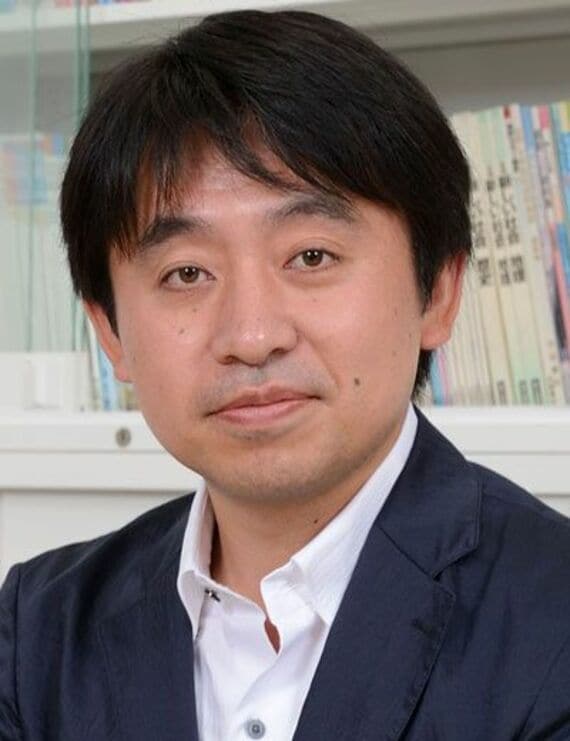
京都大学大学院教育学研究科 准教授
日本教育方法学会常任理事、日本カリキュラム学会常任理事、文部科学省「児童生徒の学習評価に関するワーキンググループ」委員などを務める。『GIGAスクールのなかで「教育の本質を問う」』(共著・日本標準)、『ヤマ場をおさえる学習評価』シリーズ(編著・図書文化)など著書多数
(写真・石井氏提供)
合理的な評価のためには、「形成的評価」と「総括的評価」とを分けることが重要だと石井氏は強調する。前者は指導を改善し、子どもを伸ばすための「見取り」。後者は形成的評価の結果として、しっかりと伸びた子どもの最終的な学習成果を判定するものだ。これらをきちんと区別し実践できれば、子どもたちの日常から評価の証拠集めをする必要もなくなり、教員にも余裕が生まれると石井氏は言う。
「日々の授業で記録や点検に追われてしまう『指導の評価化』の傾向がありますが、日々の形成的評価の目的は子どもの力を伸ばすことです。総括的評価のポイントを、思い切って重点的に設けることができれば、形成的評価はデータがなくても構わない。私は今までが、子どものすべてを総括的評価に反映しようとして、丁寧に見すぎていたと思っています」
「指導の評価化」から脱するため、石井氏が「あれぐらいがちょうどいい」と例示するのは、よくある大学のシラバスの記述だ。「ペーパーテスト4割、リポート6割」などと評価の基準が明確かつシンプルに示されており、授業態度は問われない。この場合、教員はテストで知識・技能を見定め、リポートの内容で思考・判断・表現を見ている。さらに学生が講義内容に基づき、発展した問いを立てたり考察を深めたりして優れたリポートになっていれば、そこには主体的な態度も表れていると評価できるのだ。
「大学の学びに必要なのは暗記・再生の力ではなく、学んだことを使いこなして論じる力です。だからペーパーテスト4割、リポート6割といった形で評価が行われることは、多くの人にとって納得できることでしょう。観点別評価は、毎時間証拠集めをするのではなく、単元や学期の節目といった比較的長いスパンで意識すべきものです」
知識を活用する力を促すため、2019年度、小学校の全国学力調査で知識を問うA問題と活用の力を問うB問題が統合されたことも記憶に新しい。石井氏はこれらの学びとともに、評価も時代に応じて変わるべきだと考えている。
「指導の評価化」を引き起こすもう一つの要因として、石井氏は総括的評価のための舞台が貧弱であることを指摘する。ここではオリンピック選手に例えた。
「アスリートの練習はとても地味ですが、彼らが評価を受けるのは、オリンピックというとてもダイナミックな場です。日本の学校はその逆で、豊かな授業が行えていたとしても、その評価の舞台は今も単なるペーパーテストであることがほとんど。評価のための『見せ場』が貧弱なことから、教員は日常の中からほかの材料を集めようとしてしまうのです」






























