現行民法における債権の消滅時効は10年と規定されており、それより期間の短いものが「短期消滅時効」と呼ばれている。今回の改正では、こうした債権の時効ルールが一変することになった。
Q. 債権の時効期間はどのように変わったのですか
とりわけ3年以下の時効の規定が問題視されていた。典型例は次のようなものだ。医師等に対する治療費や建設工事の請負代金は3年、弁護士報酬や商売上の売掛金は2年、ホテルの宿泊費や飲食店の代金は1年で消滅すると、それぞれ規定されている。

3年以下の短期消滅時効を規定した趣旨は、これらの債権が日常頻繁に生じ、おおむね少額で領収書なども長く保存しないのが普通で、短期間に法律関係を確定して紛争を生じさせないためだ。
帳簿を保存している商人同士の売掛債権にも2年の時効期間を適用した判例には批判が集まっていた。その他の規定の存在理由も合理性に乏しく、時代に適合していないという見方が多かった。そこで今般の民法改正では、これら特別な規定は削除され、他の債権の時効との区別をなくした。

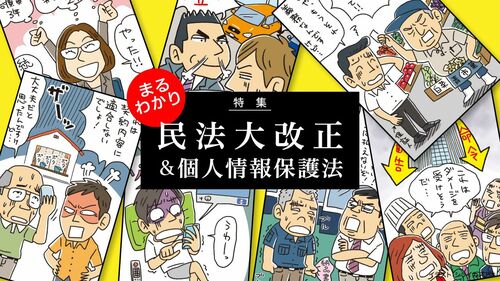








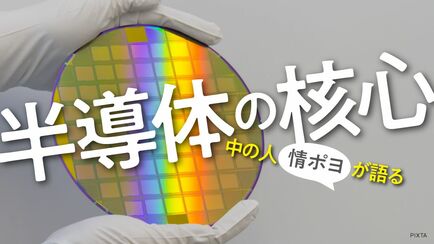






















無料会員登録はこちら
ログインはこちら