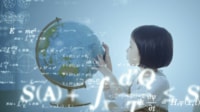授業が簡単すぎる「吹きこぼれ」を伸ばす本場米国の教育が日本へ ギフテッド教育、米・CTY学習プログラムの中身

日本では才能を見いだし育てる環境が、いまだ不十分
ギフテッド教育とは、生まれつき特別な才能を持つ子どもたちの能力を伸ばすための教育手法のこと。その目安は、かつて「IQ130以上が目安」などともいわれたが、現在は知能指数だけではなく言語能力や創造力、芸術的才能など、子どもを総合的に見て判断されることが多いという。
昨年7月、日本でも文部科学省が「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」を立ち上げた。ここでは、ギフテッド教育ではなく才能教育と表現しているが、有識者会議では特異な才能を持つ子どもや保護者、その支援団体に調査を行っており、下記のような事例を紹介している。
だが一方で、こうした子どもたちが学校では「授業がつねに苦痛でした。発言をすると授業の雰囲気を壊してしまい、申し訳なく感じてしまうので、 わからないふりをしなければならない」「学校で習っていない解法をテストなどで解答するとバツにされることが嫌だった。意味があるのかはわからないが、解き方が合っているなら正解にするべきだと思う」「精神的な発達が生活年齢よりも部分的に進んでいるため、同年齢のクラスメートと価値観や感じ方の共有ができない。共感が得られず孤独」など、困難を抱えていることもわかった。
実際、学校現場や大学、民間企業やNPOなどで、こうした子どもたちの才能を伸ばすための支援がスタートしているが、才能を見いだし育てる環境としては、いまだ日本は不十分な状況にあると言わざるをえない。
米ジョンズホプキンス大の学習プログラムCTY
そんな中、先んじてギフテッド教育に取り組んできたのが米国だ。州・学区・学校により状況は異なるものの、小・中学校、高等学校、大学への早期入学、飛び級などの「早修」 が行われるとともに、サマープログラム、各種コンテスト、放課後スクール、学校においても特性に応じた指導などが行われている。
その中の1つに、Center for Talented Youth(以下、CTY)という学習プログラムがある。CTYは、米国の有名難関大学の1つであるジョンズホプキンス大学が作ったギフテッド教育の学習プログラムだ。ほかにデューク大学やノースウェスタン大学などにも同様の教育プログラムが存在するが、1979年に作られた長い歴史のあるCTYは高い知名度を持つ。