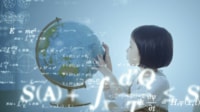授業が簡単すぎる「吹きこぼれ」を伸ばす本場米国の教育が日本へ ギフテッド教育、米・CTY学習プログラムの中身
ポール・リー氏は台湾出身だ。カナダで教育を受け、1999年に来日し、証券会社や投資信託会社で投資の仕事を続けながら、2012年に東京から香港に転勤した際にCTYの香港拠点の立ち上げに関わった。それが縁で同年、CTYのアジア・アドバイザリーボード・メンバーに就任。21年までボードメンバーを務めた後、日本に再来日し、現在はEducation Beyondの活動とともに教育とITを組み合わせたEdTechスタートアップ企業の立ち上げ準備をしている。
「9年間ほどCTYのアジア・アドバイザリーボード・メンバーとして活動しましたが、プログラムに参加する子どもたちのうち50%が中国、30%が韓国、残りがインド、インドネシア、マレーシアなどの国からで、日本からの参加はわずかでした。これはおかしいと思い、17年に日本でも説明会を開催したのですが、テストが英語だったり、夏休みの時期が米国とは異なることから、参加のハードルが高かった。ならば、日本でCTYを展開するためには違うアプローチが必要だと考え、私たちが主体となって活動をスタートさせることにしたのです」

サイモン・フレーザー大学経営学部をHonors(成績優等者)で卒業した後、ジャーディン・フレミング証券に入社。その後20年余りにわたって、フィデリティ投信、キャピタル・グループの東京および香港支社にて、投資活動に従事する。2012年には、ジョンズホプキンス大学のCenter for Talented Youth(CTY)のアジア・アドバイザリーボード・メンバーに就任。さらに22年、日本で「CTYギフテッドプログラム」を導入するため、Education Beyond代表理事に就任。CFA協会認定証券アナリスト資格を所持、ハーバード・ビジネス・スクール・アナリティクス・プログラムを修了。現在、デジタルトランスフォーメーションの分野にて起業準備をする
(写真:本人提供)
日本でギフテッド教育というと、「発達障害の子どもを対象とした教育を思い浮かべる方がいるかもしれない」と小林氏は話す。ギフテッドと発達障害の両方の特徴を持つ子どももいるため、日本では同義で語られることもあり、誤解があるという。
「ある教育研究所の調査によれば、小学校で学校教育についていけない『落ちこぼれ』は約15%いるといわれるが、それとほぼ同じ比率の約13%が『吹きこぼれ』、授業が簡単すぎてつまらないと感じる子どもたちが存在する」(小林氏)という。
CTYでは、こうした学校の授業では飽き足らず、知的渇望感を持つ子どもたちを対象としている。
「学校の教育現場で、才能がある子どもたちを特別だからと無視しないことが大切です。そうでなければ、子どもたちは孤独になって、大きなダメージを受けてしまいます。まずは、これまでの日本の教育の固定観念を解きほぐし、世界が大きく変わっていく中で、20年後の子どもたちにどんな教育をすべきかを考えることが必要なのです」(リー氏)
これまで日本の公教育は、「落ちこぼれ」の子どもたちを救うための施策を積極的に行い、学力を底上げすることに主眼が置かれてきた。その結果、OECD諸国の中でも日本は全体的に高い学力を誇ってきたが、その一方で、生まれつき能力が高く、学校の授業に退屈するような子どもたちに対する目立ったサポートは少なく、放課後の個人や家庭の努力に委ねられている状況にあった。
Education Beyondでは、こうしたこれまで日本では見過ごされてきたニーズに、まずはサマースクールのような形で対応しつつ、将来的には保護者、先生らとの協働を通し、公教育においても子どもたちの知的好奇心が満たされるような社会を目指すという。同じく理事のポピンズホールディングス代表取締役社長の轟麻衣子氏も次のように話す。