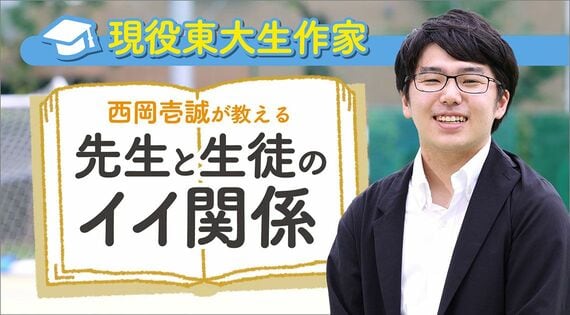ほかにもこんな例があります。学生たちはFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)やソーシャルゲームなどのオンラインゲームでパーティーを組んでプレーしていますよね。パーティーという言葉はよく使われる言葉で、みんなで集まって騒ぐ宴会のことを指すこともありますし、ゲームなどで1つの団体を指して「パーティーを組む」なんて言いますよね。
でも、パーティーって実際はどういう意味なのか、大抵は「集まり?」というくらいしか理解していなかったりします。
「パーティー」は英単語の「part」からきています。partというのは全体に対する一部分のことを指しているので、「このパート(部分)は彼が担う」なんて使い方をします。そこから派生して、「多くの人の中で一部の人が集まる」から宴会、「多くの人の中で一部の人だけでチームを組む」から団体のことを指すのです。パートタイムジョブと言えば「その人のいろんな時間の中で一部の時間だけ働く人」のことを指しますが、これも一部ですよね。パーテーションと言えば、部屋と部屋とを仕切りで分けるもののこと。これも全体の中で一部をつくるものです。
数学は「1ダース=12の秘密」を伝えよう
数学に関しても、日常生活とどうつながっているかを教えてあげるといいと思います。
例えば、12という数字はすごい数字です。何てったって、世の中にたくさん存在します。1年は12カ月ですし、星占いは12星座であり、数量の単位は1ダース=12個です。世の中のいろんな所で12という数字が使われています。これはいったい何でだと思う?という話をするのです。
12という数字は、2×2×3でできていて、約数が非常に多い数です。20までの数字の中でいちばん約数が多いですね。だから、2でも3でも4でも6でも割り切れます。そう考えると、例えば12個のお菓子があったとしても、2人でも3人でも4人でも6人でも均等に配分することが可能です。
これが10個だったら無理ですよね。10個のお菓子は3人や4人では割り切れず、「俺のほうに1つ多くよこせ!」というようにトラブルが発生してしまう可能性があります。だからこそ、12というのは多用されるもので、その次の13は素数で(つまり約数がその数字自身と1しかないので)、不吉な数であると認識されているわけですね。このように、単なる数字であっても、いろんな意味を与えることができるんですよね。
いかがでしょうか? 学生たちを引きつけるには、やはり「最初の5分」で「日常生活」とその勉強のつながりを教えてあげるといいと思います。そのためには、日常生活の中から、国語や英語、数学、理科、社会の要素を探してみるといいのではないでしょうか。神社に行けば日本の歴史につながり、花火を見れば化学につながります。勉強ってどこにでもあるのです。
「この勉強、意味あるの?」という問いの答えの中で、その科目の勉強の面白さや、やる意義を教えてあげてください!
(注記のない写真: IARC/ PIXTA)
執筆:西岡壱誠
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら