大学受験それでも「英語民間試験」受けるべき理由 共通テストで導入断念も私立中心に活用広がる
昔は、英語で聞いたり話したりする機会は少なく、読み書きを中心に勉強をしていればよかったが、グローバル化が進む中で、英語への対し方も大きく変わってきているということだ。社会に出て英語が必要になる場面が増えているのはもちろん、コロナ禍で一時止まってはいるものの日本を訪れる外国人も増えている。「サッカー選手が若くしてどんどん海外に出て、英語やイタリア語、スペイン語でインタビューを受ける時代。若い人たちにとって、もはや英語は特別なものではなく身近になっている。英語教育については、むしろ変わるべきは先生たちであり、リスニングやスピーキングに重きを置いた授業をすべき」と石原氏は警鐘を鳴らす。
社会の変化とともに、英語教育が見直されつつある中で、大学入試における英語の中身も変わっていくのだろうか。石原氏はこう語る。
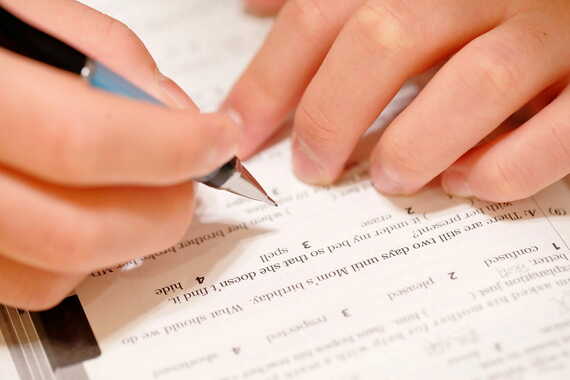
「ボリュームゾーンの受験生に対しては、実社会に即した“使える英語”が中心となっていくでしょう。SNSで簡単に国内外を問わずコミュニケーションが取れるようになり、文章を訳す力といっても、自動翻訳で十分に対応できる時代です。今はむしろリアルタイムで意思疎通できることが大事になっているのです。共通テストでも、そうした方向に進んでいくとみています。
一方、難関大学では今までと同じように長文の読み書きを含めた従来型の英語入試が残っていくでしょう。ただそれは、あくまで別の力を問うものであり、これからは基本的には聞く、話す能力を中心に問う方向へ変わっていくと考えています。その意味でも、これからは民間試験を利用することで、生徒たちに英語教育のさまざまな機会を広く提供していくべきだと思っています。入試でも民間試験が活用できる大学であれば、英語の負担を軽くすることができ、そのほかの教科に時間をかけることができる。受験生も戦略的に勉強を進めてほしいですね」
(文:國貞文隆、編集チーム 細川めぐみ、注記のない写真はiStock)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































