中大附属「図書館で授業」の浸透ぶりがスゴすぎた 司書教諭が推奨「無料で今すぐできるICT活用」
こうしたコンテンツを選定して発信するほか、生徒や教員がそのコンテンツにアクセスしやすいよう工夫することも大切だ。前述のように同校は専用のポータルサイトを作ったが、自校が選んだコンテンツのリンクボタンを学校ホームページの中に配置するなど既存のリソースを生かしたやり方もある。このほか、「Webサイトの紹介シートやQRコード集を作成し、図書館での掲示や配付をすることもお勧め」と、平野氏。授業に必要な情報への誘導策としても有効だという。

(資料:中央大学附属中学校・高等学校図書館提供)
これからの時代、学校図書館を担う司書教諭や学校司書に求められることは何だろうか。
「今後はネットワーク上の膨大な情報源から、正確で信頼できる情報源や学習用コンテンツを選定する必要があるので、情報を取捨選択する識見が重要です。これまで図書資料の選定を担ってきた多くの経験から、司書教諭や学校司書にはそういう能力が備わっていますので、ネットワーク情報源の選定も適任と考えています。
そして、高度なICTスキルは必須ではありませんが、図書館内で課題レポートの作成に取り組む生徒も多いので、文書作成・表計算・プレゼンテーションソフトの基本的な知識は備えておきたいですね」

また、平野氏は、自身が05年から専任の司書教諭を担ってきた経験も踏まえ、学校図書館のあるべき運営についてこう語る。
「学校によって司書教諭や学校司書の配置状況、業務内容が異なっているのが現状ですが、本来なら生徒や教員がいつでもわからないことを聞きに来られるよう、スタッフは常駐であることが望ましいです。
また、教員としてつねに図書館で授業を見聞きし、生徒や教員とのやり取りの中から長期的な視点で運営を考える人がいるべきで、そのためにも司書教諭は専任であったほうがいい。専任だと成績をつけることがないため生徒も話しやすいようで、何でも聞きに来てくれますよ。
図書館と教職員との連携も大切です。図書館スタッフが教育活動の内容にアンテナを張ることも重要ですが、教科担当の先生方も、本だけでなくネットワーク上の学習用コンテンツを司書教諭に紹介してほしい。そうすることで、アナログとデジタル両方の資料が司書教諭と学校司書によって整理され、学校図書館はハイブリッドな『学びの拠点』へと進化していけるでしょう」
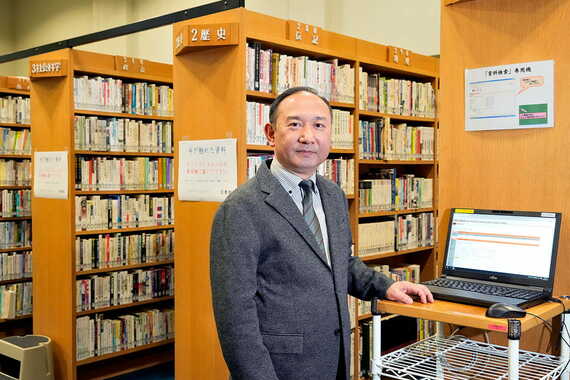
中央大学附属中学校・高等学校の司書教諭。理科教諭(生物担当)を経て、2005年から専任
(文:編集チーム 佐藤ちひろ、注記のない写真は梅谷秀司撮影)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























