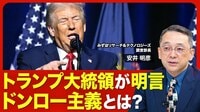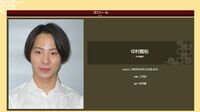国際数学オリンピック金メダリスト中島さち子氏が語る「STEAM教育の本質」 「未来を生き抜く力」はプロジェクトで習得せよ
では現場の先生たちはSTEAM教育をどう捉えればいいのか。まずは、「教える」ことの意義に変化が起きていると認識すべきだろう。
「これまでは、知識を暗記することに評価の力点が置かれていましたが、情報化社会となった今、頭の中に知識を蓄える価値は相対的に低くなりました。なぜなら、インターネット検索をすればすぐに必要な知識が得られるからです」

(撮影:梅谷秀司、今井康一)
そう指摘するのは、石戸氏。もはや、教壇の上から教員が知識を与える時代ではなく、子どもたち自身が興味ある課題に取り組んでいく中で、成長を促していく時代だという。そして、中島氏は今後、先生の役割はこれまで以上に変化していくと指摘する。
「STEAM教育などのプロジェクト型学習では、先生にとっては自分の専門外の領域と接続されることになりますから、聞かれても答えられないことが出てくるでしょう。それでもまったく問題はありません。先生たちは思考モデルや調べ方、社会との接続の場などを準備し
そうすることで、子どもたちが主体的に考え、課題を解決する能力が身に付くからだ。この能力は「未来を生き抜く力」とも言い換えられるかもしれない。
「これから教育を受ける子どもたちは、2100年まで生きていくんです」と語るのは前編で登場したNPO法人みんなのコードの利根川裕太氏。その頃には、今では想像もできないほど社会全体が変化を遂げているのは確実であり、そのときに必要とされる力を今予想することは不可能だ。だからこそ、プログラミング教育を含めたSTEAM教育で、未来を生き抜く力を育んでいくことが求められている。
(注記のない写真はiStock)
制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら