独学で東大合格!成功の近道は「100人分の合格体験記を読むこと」 不安を解消、学びを得る"5つの活用法"《受験勉強の序盤にまず読む》
ポイント③ 具体的な参考書を挙げているものを選ぶ
合格体験記には、心構え中心の抽象度が高いものもあれば、使用教材や学習プロセスまで踏み込む具体度が高いものもあります。
私のおすすめは、具体的に参考書名などを挙げているような合格体験記です。
このような合格体験記を複数個読むことによって、受験生の間で定番となっている参考書や学習法が浮かび上がります。これにより、今後の学習計画において「大外し」を避けやすくなります。
また、このように具体的な書名を挙げる合格者は、自身の合格を可能な限り網羅的かつ客観的に描写しようとする傾向があり、質の高いことが多いと感じます。
前述のように、合格体験記を読むことの本義は、複数の体験記に共通する部分から学ぶことにあります。
「定番となっているもの」と「人によって扱うかどうかが分かれているもの」と「扱っている人が珍しいもの」の違いを見出せるようになることが肝心です。
ポイント④ 「不合格体験記」からこそ学ぶ
ときには合格体験記よりも価値があるのが「不合格体験記」。
合格した話ばかりを読んでいても、真の要因が何であったかを特定することは難しい。不合格者と比較をすることで、初めて合格者のみに共通する性質が浮かび上がってきます。
例えば、私が感じた不合格者にありがちな特徴は次のとおりです。
・文章を読むスピードが遅く、日々文章を読む量が少ない
・英数の基礎固めが不十分なままになっている
・添削指導など、他者の目を取り入れる機会が少ない
こういった、“受験の落とし穴”を把握するためにも、不合格者の特徴を知っておくことが大切です。
ただ、不合格体験記の入手は、合格体験記に比べると少し難しいもの。大学受験においては、浪人生の合格体験記、中学・高校入試においては複数受験したうえで、受かった学校と落ちた学校がある生徒の合格体験記が参考になるでしょう。
昔に比べて、インターネットにはさまざまな体験談が転がっているので、不合格者の話も見つけやすくなりました。
ポイント⑤ 「受験の雰囲気」に注目する
合格体験記の多くは、受験数日前~当日の記録がとくに生々しく、単純に読み物としても引き込まれます。
やはり、多くの受験生にとって、第1志望の入試当日は緊張するもの。ほとんどの人にとって初めての経験でもあるため、なにかしらのミスをしてしまうことはあります。
そのような緊張とミスを避け、もし何か失敗してしまったとしても損失を最小限に抑えるためには、どれだけ克明に入試当日をイメージできているかがとても大切です。
「塾発信の体験記」は要注意
ここで注意したいのが、塾や予備校が出している体験記です。もちろん、掲載数が多いという明確な利点はあります。
しかし、その塾に通っている場合を除いて、必ずしも再現可能性が高いとは限らないと感じます。
塾への忖度が入ってしまいがち、というよく言われる問題もありますが、何よりも塾で取り組んでいたことが“あたりまえ”とされやすく、なかなか触れてくれないものが多いと感じています。



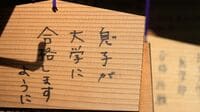



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら