特別支援学級の教員が懇願「〇組"さん"と呼ばないで」、学校内でよそ者扱いに怒り 直近10年で特別支援教育を受ける子どもは倍増
別の公立中学校で通常級の教員をする佐藤花子さん(仮名)も「〇組“さん”」問題は存在すると指摘する。
「私の中学校では、今年度に初めて支援級が設置されました。他校では差別的に最後の組が振り分けられることが多いということで、逆に支援級を1組にして、通常級は2組から編成されました。年度頭の職員会議で管理職に『絶対に1組“さん”と呼ばないように』ときつく言い渡されました。それって、むしろ教員の中に『〇組“さん”』問題が根強く残っている証拠ですよね」(佐藤さん)
特別支援教育の充実は教育全体の質向上に寄与
一方で、疎外感を感じたことがないという支援級の教員もいる。中部地方の公立小学校で支援級を担任する黒部五郎さん(仮名)だ。
「この10年の間で、1つの学校にある支援級の数も、担当する教員の数も増えました。どのクラスにも支援が必要な子がいる状況で、支援級の先生との連携が通常級の先生にとっても必須になっています。世間においても、保護者の間でも支援級の認知度が高まる中で、自分の周囲では通常級と支援級の担任の間で壁を感じることはありません」
文科省は2022年、「今後採用するすべての教員に特別支援教育の担任を2年以上経験させる」よう通知を出し、特別支援教育に本腰を入れる姿勢をみせている。子ども一人ひとりの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現を目指す中で、特別支援教育の充実は教育全体の質向上に寄与すると考えてのことだろう。今や若手で専門的知識を持った状態で支援学級に入ってくる人もいるという。
「誰もが支援級の担任になる可能性があるにもかかわらず、支援級と通常級の先生との間に壁があることに驚きです」と黒部さんは話す。
特別支援教育を受ける児童生徒が増える中で、学校運営においても1つの柱として位置付けていく必要がある。しかし、現状は通常級の運営に手一杯で支援級から目を背けてはいないか。これまでの風習だからと、腫れ物扱いと取られかねない振る舞いをしていないか。いま一度、振り返って考えてほしいところだ。
だが、教員の配置についても、新人や臨時的任用教員中心の配置で学級運営がままならない、授業もカオスな状態だと訴える支援級の先生がいる。後編に続く……。
(注記のない写真:くにさん / PIXTA)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




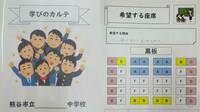



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら