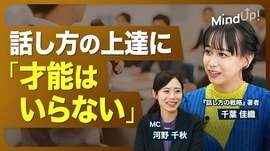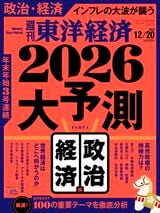「学童落ちた」小1・小4の壁の現実、なぜ保育所より軽視?学童待機児童3年連続増加の背景 指導員の半数が年収150万円未満の悲哀
指導員の給与を上げるには、どのような改善策が考えられるのだろうか。安部氏は次のように述べる。
「子どもが来所していない時間帯に行う準備作業なども勤務時間に含められるよう、指導員が1日6時間を超えて働けるように自治体の条例を見直すのも1つの方法です。首都圏の保育所では、保育所が借り上げた社宅に対して補助金が支給される家賃補助制度が保育士確保につながった例もあるため、国と自治体は学童保育に関しても家賃補助などを含めた処遇改善策を打ち出すことが望ましいと言えるでしょう」
放課後の子どもの権利を保障するという視点からの環境整備を
「学童保育は数の確保と同様に、質の保証も重要」と安部氏。そのためには、「放課後の子どもの権利を保障するという視点から、子どもが『行きたい』と思える遊びと生活の場としての学童保育を整備していく必要がある」と話す。
2023年12月にはこども家庭庁が「こどもの居場所づくりに関する指針」を閣議決定し、その内容を受けて、2025年4月より改正された「放課後児童クラブ運営指針」の施行が開始された。これらの指針が示されたことは、自治体に放課後行政への積極的な取り組みを促す契機になると安部氏は期待を寄せる。
「『こどもの居場所づくりに関する指針』には、子どもや若者の声に耳を傾け、彼らの視点に立った居場所づくりを推進していくことが盛り込まれました。それを受けて、『放課後児童クラブ運営指針』は、学童保育を子どもが自らの権利を実感できる場にすることを目指す内容に改正されました。これらの指針の理念でもある国連子どもの権利条約第31条には、子どもが休息・余暇をもつ権利、遊ぶ権利、文化的・芸術的生活に参加する権利が記載されており、これらの権利は学童保育においても保障されるべきものです。今回の指針の改正により、それぞれの自治体が子どもの権利に配慮した放課後行政を推進していくことが期待されます」
学童保育を卒業した高学年の子どもも利用できる放課後の居場所を確保するには、「学童保育から児童館の自由来館などへの移行も有効」と安部氏は提言する。ただし、居場所の整備は大人の都合で進めずに、子どもたちの意見を聴きながら進めていく必要があると強調する。
「こども基本法の第11条には、こども施策の策定・実施・評価にあたってはこどもや関係者の意見を反映することが国や自治体に義務づけられています。大人目線の待機児童問題として捉えるのではなく、学童保育を子どもが『行きたい』と思える楽しい場所にするにはどうすれば良いかを子どもに聴きながら、子どもの権利を保障するために必要な環境を整備していくことが重要です」
(文:安永美穂、編集部 細川めぐみ、注記のない写真:ペイレスイメージズ1(モデル) / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら