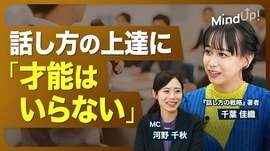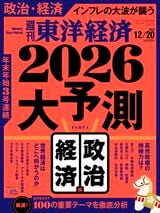「学童落ちた」小1・小4の壁の現実、なぜ保育所より軽視?学童待機児童3年連続増加の背景 指導員の半数が年収150万円未満の悲哀
東京に住むライター・コラムニストのせきねみきさんは、今年この「小4の壁」にまさに直面することとなった1人だ。
「4月に4年生になる長男が学童に入れませんでした。学童は1年生のときから通っていて、実は3年生のときも入れなかったのですが、待機が少なく昨年は5月から利用できました。今年は待機児童が私の前に30人以上もいるそうで、繰り上がりでの利用は期待できないと思います」
せきねさんが住む地域では、1〜2年生の希望者は大体学童に入れるという。たしかに4年生で学童に通う子は少ないというが、当初は学童が利用できない生活に不安を抱えていた。ただ、子どもが友だちと遊ぶ約束をしてくることも増え、現状で困ったことは起きていないという。
「当面の悩みは、夏休みなどの長期休暇の過ごし方をどうするかです。これまでは毎日学童に行っていたので、まだ何も考えていません。塾には通っておらず、サマーキャンプなどに行かせるのも一時的な対応になってしまうため、ひとまず児童館に遊びに行ってもらうのがいいのかなと思ってはいるのですが……」
夏休みとなると、放課後だけでなく丸1日を過ごす居場所について考えなくてはならない。せきねさんの住む地域にある児童館では、併設の学童エリアには入れないものの、事前申請をすればお弁当を食べて1日過ごすことも可能だというが、まだ頭を悩ませているようだ。
「フリーランスとして働いており、開業届に記載されていた住所の兼ね合いで在宅扱いと判断されたようです。取材で外に出ることも多いですし、今後は下の子が学童を利用することも考えると、自治体には家庭の実態にあった対応、支援をしてほしいと願っています」
保育所と比較して学童保育の待機児童が多いのはなぜ?
一方、保育所の待機児童は、ピークだった2017年から10分の1以下に減っている。2024年には全国で過去最少の2567人にまで減少しているが、学童保育の待機児童数は1万7686人と増加傾向にある。

その背景について、安部氏は次のように話す。
「受け皿の拡大に加えて、就学前人口が急激に減少したことで、保育園の待機児童数は減少しました。一方、学童保育の待機児童数が増加している要因としては、共働き世帯の増加、女性就業率の上昇が考えられます。かつては出産・子育ての時期と重なる年代では女性の就業率が落ち込む『M字カーブ』が見られましたが、現在は子育て中も働き続ける女性が増えています。また、厚生労働省が『放課後児童クラブ運営指針』を策定して、国として放課後児童クラブに関する運営および設備についてのより具体的な内容を定め自治体に発出したのは2015年からなので、整備がまだ追いついていない部分もあるように思います」
また、安部氏は「学童保育の待機児童数を把握していない自治体や、設置していない自治体、廃止した自治体もある。施設単位で申し込みをする場合は、その施設に空きがないと申し込みを諦めてしまうケースもある」と、潜在的な待機児童の数はさらに多い可能性にも言及する。
「学童保育は、保育所のような『児童福祉施設』ではなく、いち『事業』に過ぎないため、予算規模も小さく、自治体の中で軽い位置づけになりがちです。学童保育は学校と家庭の間の『おまけ』のような存在と見なされやすく、これまでは整備に力を入れてこなかった自治体が多いと言えます」