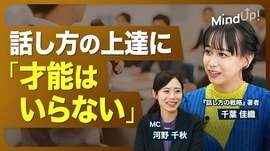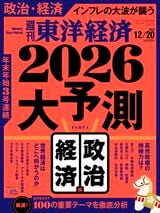「学童落ちた」小1・小4の壁の現実、なぜ保育所より軽視?学童待機児童3年連続増加の背景 指導員の半数が年収150万円未満の悲哀
学童保育の実態は自治体ごとの差が大きい
学童保育の整備状況に関しては、「地域差が大きい」と安部氏。「学童保育は、厚生労働省の『放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準』に基づいて、それぞれの基礎自治体が条例を制定して運営しているものなので、その実態は自治体によって異なる」という。
「長期休み中の昼食の提供や開所時間の延長などに対応する独自の認証制度を2025年度より導入する東京都のように、国の基準よりも手厚い運営基準を設けている自治体もありますが、そもそも学童保育が設置されていない自治体もあります。また、2024年5月時点で待機児童数が1000人を超えているのは、東京都、埼玉県、千葉県、兵庫県の4都県で、都市部において待機児童が多い傾向が見られます」
子どもの放課後の居場所としては、すべての児童を対象として、地域住民などが学習支援や遊び、体験活動などを行う「放課後子供教室」も実施されている。
ただ、安部氏は「『放課後子供教室』は地域の人の善意によって運営されているケースが多く、毎日実施されているとは限らない。また、学童保育には配置が義務づけられている、保育士や教員などの有資格者で所定の研修を受けた『放課後児童支援員』によって運営されているものではないため、学童保育に代わる受け皿にはならない」と指摘する。
「この給与では生活が困難」、指導員不足を解決するには
学童保育の充実を図るうえで課題となるのが、指導員をいかにして確保するかだ。人材確保が困難になっている要因の1つに、指導員の給与水準の低さがある。
全国学童保育連絡協議会の調査では、週20時間以上勤務する指導員(非常勤も含む)の約半数は年収150万円未満、約6割の職員がワーキングプアと言われる年収200万円未満であることが明らかになっている(「学童保育(放課後児童クラブ)の実施状況調査結果について(2025年2月)」における2017年度の年間勤務実績より)。

「指導員の勤務時間を1日6時間未満としている自治体が多いことも、給与水準が低くなっている一因だと考えられます。教職課程で学ぶ学生の中には、放課後児童支援員の仕事に興味を持つ人もいますが、この給与では生活が困難だという理由で教員志望に切り替えることがほとんどです。学童保育の現場からは、『70代以上の応募者が多く、若い世代・中堅世代の人材が確保できない』との声が多く聞かれます」
給与水準が低くなっている背景として、自治体が放課後行政に十分な予算を確保していないことに加えて、学童保育の指導員の専門性が軽視されている傾向があると安部氏は指摘する。
「学童の指導員は、放課後の短い時間の中で子どもとの関係性を築き、複数の学年の子どもたちに目を配り、障害のある子への対応も行います。教員や家庭と連携する場面も多く、高い専門性が求められる仕事なのですが、保育士や学校教員に比べると下に見られてしまう風潮があり、処遇改善も進んでいないのが実情です。国は指導員の処遇改善を行った自治体へ補助を出す取り組みをしていますが、利用している自治体は一部にとどまります」