波乱を呼んだ共通テストへの「情報」追加、公平性や必要性は?識者が論じる賛否 変わる大学入試、新教科追加の意義を問い直す
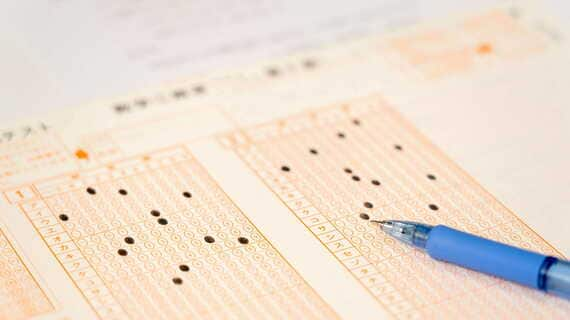
[反対派]学校間・地域間の格差が大きく、公平ではない
共通テストに「情報Ⅰ」を追加することは「拙速」と主張しているのは、「入試改革を考える会」。同会は2019年10月に結成され、当初予定されていた英語民間試験の導入など共通テストの問題点を指摘してきた。なぜ「拙速」なのか。代表の大内裕和武蔵大学教授に聞いた。
――なぜ「情報Ⅰ」の追加は「拙速」なのでしょうか。
まず、教育体制が整っていません。文部科学省の調査では、2022年5月の時点で情報科の担当教員のうち、正規免許を持たない公立高校の教員が16.3%でした。2023年には、この割合が4.4%まで減りましたが、資格を持たない教員に教えられる生徒はまだいます。学校間、地域間の教育格差が大きく、まったく公平な状態ではありません。

武蔵大学教授
1967年神奈川県生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程を経て、2022年より現職。専門は教育社会学。主な著書に『教育・権力・社会』『なぜ日本の教育は迷走するのか』(以上、青土社)、『ブラックバイトに騙されるな!』(集英社クリエイティブ)などがある
(写真:本人提供)
共通テストは日本全国でやるのですから、北海道から沖縄まで教育体制を整えてからやるべきです。だから私たちは「拙速」だと訴えています。
――「情報」の正規免許を持つ教員がすべての高校に配置されれば、共通テストに追加すべきでしょうか。
それが共通テストに追加するうえでの最低ラインですが、私は2つの理由から、共通テストへの追加は望ましくないと思っています。1つは、科目数の多さです。従来の5教科7科目でも大変なのに、今年からは6教科8科目が基本となります。
これは、明らかに過大な負担です。やるべきことが多くなると、1つひとつの科目の学習にじっくり時間をかけられず、表面的な理解や暗記になりがちです。他科目、とりわけ大学での学習の基礎となる国語や数学、英語の学力に悪影響を与える可能性は否定できないと考えます。
もう1つは、果たして大学での学びで要求されるレベルの問題が出題できるのかということです。大学入試は、入学後に必要な学力を持っているかを選抜する試験です。しかし、試作問題を見た限り(編注:取材は共通テスト前に実施)、応用性や発展性に乏しく、社会生活上の常識を問う問題が多く出題されています。
それは無理もないんです。なぜならば、「情報Ⅰ」は基本的に高校1年生で学ぶ教科です。すなわち、その予備知識は義務教育である中学で得るものを前提としています。内容の多くは社会生活上の常識レベルであって、大学での高度な研究に求められる水準ではありません。
































