塾講師も懸念「中学受験組」の暴言や学級の荒れ、ストレスの矛先は小学校に 子の人格形成を重視し「高校受験」を選ぶ家庭も
中学受験のストレスの矛先が向かう、小学校現場
小学生は精神的に未熟である。学力が比較的高い小・中学生が集まる学習塾で指導をしているからこそ、私はこの事実を断言できる。
小学生は、ときに平気で、自分よりも劣っている子をバカにするような言動を取る。授業外でのやり取りも含めて丹念に観察している学校の先生方も、それは容易に気付けるだろう。自我が強まり、自分の優位性をひけらかそうとするのだ。その裏には、視野の狭さや他者への配慮の欠如といった社会的スキルの未熟さが透けて見える。
ここで指摘したいのは、学力の高さと社会性の未熟さというアンバランスさだ。にもかかわらず、塾や保護者は前者だけをより一層伸ばそうとする。そうした歪みが、前述の名門中学生の暴言や中学受験層のマウントなどにつながっていると感じる。
そして、その歪みのしわ寄せが、とりわけ小学校という場にきているように思う。
私は塾講師としての仕事の傍ら、ライフワークとして転居相談や、都内公立小・中学校の授業見学を続けており、そうした立ち位置からではあるが、保護者や学校の変化がよく見える。近年、都内の公立中学校はかつての「荒れた時代」から大きく改善し、非行生徒も激減して、すっかり落ち着きを取り戻している。
一方、Xの約4万9000人のフォロワー(2025年1月現在)の情報網や、2年間で400人以上の保護者の相談に応じていく過程で、「〇〇小学校の〇年〇組が荒れている」という生々しい声も届くようになった。
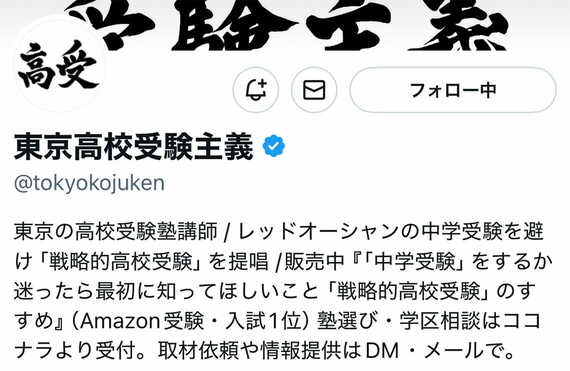
(写真:Xより)
都内の保護者からはこんな声をよく聞く。
「受験率の高い公立小学校では、中学受験組が授業中に騒いだり、ストレスで荒れたりすることがあった。しかし、公立中学校に進むと驚くほど落ち着く。荒れていた子たちはみな、私立中学に進学していった」
小学生にとって、現代の中学受験は莫大な拘束時間を伴い自由を奪う。家に帰れば、伴走する保護者とともに受験勉強に明け暮れ、ストレスの矛先を学校に向けることも少なくない。もちろん、それが許されるべきではないが、社会性が未熟な10歳、11歳に成熟した振る舞いを求めるのは酷だと言わざるを得ない。そして、子どもたちのストレスを受け止める負担を背負わされているのが、小学校の現場で働く先生方であることを忘れてはならない。
中学校の3年間で大きく変わる「社会性」
こうした小学生時代の未熟さは、成長とともにどう変化するのか。それを実感したエピソードがある。高校受験を目指す進学塾で、公立中学3年生の男子数人と話したときのことだ。
「偏差値の低い人は努力不足だと思うか?」と、ふと私が問うた。
C君が、次のように答えた。
「努力不足の人もいるかもしれませんけど、ここに通う人は、一番下のクラスの人でもめちゃくちゃ努力してますよ。正直、俺よりも努力してる人はたくさんいます。俺は勉強ができるほうですけど、たまたま勉強の才能に恵まれただけです」
D君もこう続けた。
「〇〇とか、毎日自習室に来てるじゃないですか。勉強は得意じゃないですけど、あいつの努力を見て『努力不足』なんて言えるやつ、誰もいないですよ」
周りの生徒たちも口々に「うんうん」とうなずく。やがて話題は、彼らが学校生活で感じる家庭の経済格差へと広がっていった。「学校に家庭の事情で塾に通えずに無料塾に行っている同級生がいる」といった言葉に、彼らの視野の広さを感じた。
小学生の頃には勉強ができない子に思いをはせることができなかった子も、中学3年生になる頃には、他者を思いやったり、経済的事情を理解したりする視野の広さを身に付けていく。中学校の3年間という期間に子どもたちは社会性を大きく成長させるのだ。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら