聞こえているのに聞き取れない?聴覚検査は正常な「聞き取り困難症」の実態 聞き間違いは"天然キャラ"のせいじゃない
──LiD/APDの定義で「自覚症状」が挙げられているのはなぜですか?
障害のある人の対応は従来、医学的モデルの疾患ベースで考えてられてきました。それが今では、「その人が何に困っているのか、困りごとベースで考えよう」という流れがあります。耳鼻科も同様で、欧米では「難聴の対応は、聴力検査の結果より本人の自覚が大事」とされています。聴力検査で正常範囲でも、その人が聞き取りに困難を感じているのであれば、何らかの対応をしましょう、というのがわれわれの考え方です。LiD/APDの定義には異論もありますが、これまで「聴力検査で問題がないので、聞こえにくいのは気のせいです」と言われてきた人たちの背景や支援にもしっかり対応しようということなのです。
自覚症状が大事だが、子どもほど聞き取りにくさを自覚しづらい
──聞き取りに困難を感じている人の割合はどのくらいなのでしょうか?
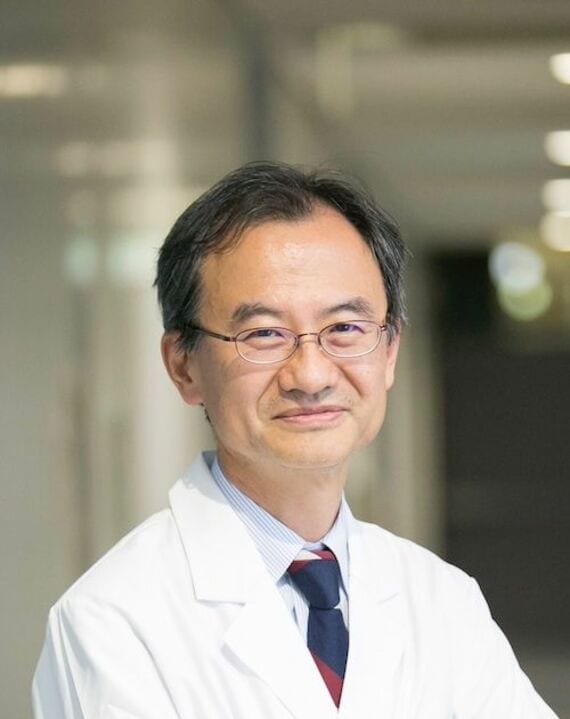
医誠会国
大阪公立大学大学院医学研究科 特任教授(聴覚言語情報機能
(写真は本人提供)
われわれが、難聴と診断されたことが「ない」18〜
──LiD/APDと見られるお子さんの割合はどのくらいなのでしょうか?
大阪教育大学附属学校の小1〜高3を対象に、3年にわたってアンケート調査を行った結果、われわれのLiD/APDの定義に当てはまりそうな生徒は、回答者の21.1~24.7%にあたりました。もともと聞こえに関心がある生徒が回答しているというバイアスはあるものの、4〜5人に1人が聞こえに困っていると思われます。
小さいうちは聞こえにくさを自覚しにくく、年齢が上がるにつれて自覚症状が出てきます。子どもが小学校1年くらいまでは親子で症状の見立てが合うものの、それ以降は乖離が出てきます。「自覚症状あり」の子どもが右肩上がりで増えるのに対し、「子どもの聞こえが気になる」という親は増えません。つまり、子どもは困っているが親は気づいていない、というケースがあるということです。
──聞こえにくいまま過ごしているお子さんも多そうですね。
小学生などの早い段階でLiD/APDが見つかるケースは少ないです。ただし、発達障害のお子さんなどでコミュニケーションの問題をきっかけに調べた結果、比較的早く判明することともあります。






























