教育先進国フィンランド、ゲームも活用「学習困難児への介入」研究最前線 子どもによって異なる効果、違いの要因に迫る
これまで、日本だけでなく、世界各国で学習障害を含む学習困難に関する支援や介入方法についての研究が行われてきました。中には、有効な介入方法も数多く開発・紹介され、実際の学校現場の教育実践に適用されています。
一方で、同様の介入方法を用いても、効果のある子どもとまったく効果を示さない子どもがいるのも事実で、その要因として神経発達、認知発達、自己統制、社会情動的発達、学校環境、家庭環境などさまざまな背景が関わっていると指摘されています。こうした多様な要因と介入方法、および学習困難のその後の発達がどのように関わっているかを、包括的に捉えた研究はまだまだ少ないと言われています。
そうした現状から、InterLearnでは、学習困難に関わる多面的なデータを収集し、支援の効果に影響を及ぼすさまざまな要因を網羅的に明らかにすることを目指しています。具体的には、6つの下位プロジェクトに分かれてデータの収集や分析等を行っています。プロジェクトの内容は、妊娠期から学齢期まで縦断的に子どもの発達を追っていくものや、脳科学と学習困難の関係を研究するものなど多岐にわたり、私はデータ分析などを担当するプロジェクトに所属しています。
その中に、問題行動、読み困難、算数困難がある子どもに介入を行い、その成果とさまざまな要因との関係を明らかにしようとするプロジェクトがあります。本稿では、今年2月から実際に介入が始まった、読み困難(Reading difficulties)がある子どもへの介入研究について紹介したいと思います。
クラス担任を持たない「特別支援教員」たちが協力
私の前回の記事(公認心理師が驚いた「フィンランドのインクルーシブ教育」、日本とは何が違う?)でもお伝えしたように、フィンランドの学校にはクラス担任を持たない特別支援教員が配置されており、特別な支援を要する子どもの対応に当たっています。
読み困難への介入研究は、そうした地域の小学校に勤務する特別支援教員との協力の下に行われています。この研究に関心を持ってくださる方を募り、今春はおよそ30名の特別支援教員の先生が参加してくれています。
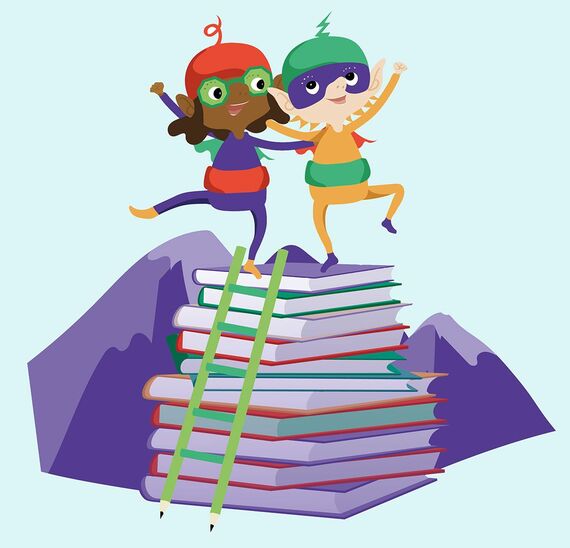
研究の流れとしては、まず特別支援教員が担当する3、4年生で、読みに困難を抱える児童を挙げてもらい、昨年の秋にその子どもたちのアセスメントを「読み課題」を用いて行いました。そして、アセスメントの結果を基に、支援が必要と判断され、介入からより読解力の発達に効果を得られそうな子どもを選出しました。
その後、子どもと先生を対象に、介入前の測定を実施。児童からは、読みの能力を測る課題だけでなく、学習における自己効力感やモチベーションといった情動面に関わる質問や、学習環境や友人関係に関わる質問など幅広く聞いています。先生からもこの児童に関わる情動的・環境的な要因に関する情報を集めるだけでなく、これまでの経験やストレス、教えるに当たっての自己効力感など、先生自身への質問にも答えてもらいました。
また、先生たちを対象に、どのように読み困難への介入を行ってもらうかを研修しました。本研究では、新しい介入方法を開発することを目的とはしていません。私が勤務するユヴァスキュラ大学でも、長きにわたり読みや算数に困難のある子どもをサポートする方法やツールが研究開発され、それらの有効性がすでに研究で示されているからです。そのため、すでに有効性が示されているツールや取り組みを組み合わせてマニュアル化された介入プログラムを、先生たちに実践してもらっています。






























