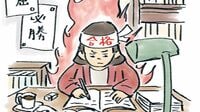「無料塾」の先駆け「八王子つばめ塾」創設者が語る、教育格差解消に必要なこと 食料支援と奨学金も実施「教福中道」こだわる訳
大学卒業時は就職氷河期で、教員採用試験に合格できず、私立高校で社会科の非常勤講師になった。しかし、収入が不安定なため、映像制作会社の正社員に転職。紛争地帯や東日本大震災などを取材する中、「人の役に立つことをしよう」と決意し、2012年に無料塾を立ち上げた。現在も東京薬科大学と私立高校の非常勤講師、病院でのアルバイト、講演料などで生計を立てながら無料塾の運営を続けている。
創設12年目となる今、小宮氏は、行政・学校・民間にはそれぞれにできることがあるという思いを強くしている。
厚生労働省の2021年調査によれば、子どもの貧困率は前回調査の14%から11.5%と改善傾向にあるものの、一方で大学進学率は57.7%と過去最高を記録し、家庭の経済状況による教育格差は拡大していることがうかがえる。
格差を埋めるために必要なことについて、小宮氏はこう語る。
「行政がやると効果的なのは一律一斉の支援なので、すべての子どもが平等に支援されるような政策を打ってほしいです。例えば、東京都は2024年4月から私立高校を含む高校授業料を実質無償化としましたが、本来なら高収入層に授業料の支援を広げるよりも、給食費無償化などのほうが優先度は高いはずです。また、東京都は都立学校の設置者なのですから、都立高校の改修や学びの充実にお金を使う必要があるのではないでしょうか」
学校教育でも少人数体制を進めるなど、より個別指導に近い形で、教育の質を担保すべきだと小宮氏は考えている。
「とはいえ、教員の業務は雑用も多く、保護者対応や事務など負担が大きすぎます。ソーシャルワーカーや弁護士、事務スタッフなど、教員以外の支援者も増やして負担を軽減させ、本来の仕事である子どもと向き合う時間を取れる体制にする必要があると思います。そのためにも、日本はもっと教育にお金をかけるべきではないでしょうか」
教育格差をなくすため各地に無料塾を
つばめ塾のこれまでの成果について、小宮氏はこう話す。
「ボランティア講師は、生徒にとって親でも先生でもない大人。そうした社会人との出会いは、経済的に苦しい家庭の子どもはとくに少なく、つばめ塾は貴重な場になっていると思います。中には、講師との関わりを通じて大学進学への意欲が芽生えた子や、英語を使う仕事に就きたいと考えるようになった子もいます。そんなふうに、つばめ塾は将来への種まきをする場所。それがいつどんな形で芽を出すかは、誰にもわかりませんが、これまで325人の子どもたちに種まきができたことこそが、つばめ塾の成果だと思っています」
無料塾の輪は広がっており、小宮氏が相談を受け、設立をサポートした無料塾は50を超える。
「これまでは八王子市を中心に展開していましたが、まだまだ無料塾がない地域もあります。それもまた教育格差につながると考え、つばめ塾の多拠点化を進めています。すでに東京都区部で活動する東京つばめ塾もありますが、大阪府枚方市でも枚方つばめ塾を開校しました。今後はさらにあちこちにつばめ塾をつくっていきたいと思います」
子どもの将来に大きな影響を及ぼす教育格差。解消に向けては子どもが安心して学べる環境の整備が必要であり、行政や学校とは別の民間だからこそできる無料塾ならではの支援は、今後さらに重要性が増していきそうだ。
(文:吉田渓、注記のない写真:編集部撮影)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら