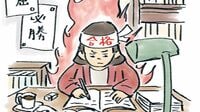「無料塾」の先駆け「八王子つばめ塾」創設者が語る、教育格差解消に必要なこと 食料支援と奨学金も実施「教福中道」こだわる訳

認定NPO法人八王子つばめ塾理事長
1977年東京都生まれ。都立南多摩高校卒業後、国学院大学文学部史学科に進学。大学卒業後、私立高校の非常勤講師(地理歴史)や映像制作の仕事を経て、2012年に八王子つばめ塾を設立。NPO法人化した2013年より現職。現在はNPO法人東京つばめ無料塾の理事長を兼任し、東京薬科大学と私立高校で非常勤講師を務める。著書に『「無料塾」という生き方 ― 教えているのは、希望。』(ソシム)
(写真:本人提供)
「私たちが目指す支援が自由にできなくなってしまうからです。例えば、自治体の受託事業として行う場合、場所や開塾の頻度を決められてしまうほか、受験支援はできないなど、指定された枠から外れることはできません。経済的に苦しい家庭の子に必要なのは、公立校の受験対策も含めた個別の学習支援です。公的資金を受けてしまうと、必要な学習支援ができなくなる可能性が高いのです」
公的資金を受けない理由はもう1つある。それは、学習以外の支援も行っているためだ。
「環境が不安定だと勉強どころではなくなりますから、子どもたちに最も必要なのは家庭の安定です。そればかりは私たちにはどうすることもできませんが、私自身が貧困家庭で育っており、少しでも経済的な支援があることが重要であると身に染みて理解しています。そこで、つばめ塾では『学習支援』『食料支援』『奨学金』の給付を3本柱として活動しているのです。この3つは偏ることなく、同じ割合で行っています」
つばめ塾では全国の農家や企業から寄付された米やパスタ、菓子などを生徒に配布している。昨年1年間で配布した米は2.2トンに上る。
「公的支援は公平が原則ですから、家庭の状況に応じて多く配るといったことはできませんが、私たちは子どもが多い家庭には多めにお米やお菓子を渡すことができます。また、つばめ塾では希望者に返済不要の奨学金を給付しています。中学生には塾に来る交通費を全額支給するほか参考書や問題集をプレゼント、高校生には月額3000円を支給。高校・大学に進学した際には教科書代として2万円を給付しています。こうした奨学金制度も公的支援を受けていると自由にできませんから、寄付のみで賄っているのです」
このようなあり方を小宮氏は、「教福中道」と独自の言葉で表現する。教育と福祉の両方を行っていくという意味が込められている。
貧困家庭に育ったからこそ「無料塾」にこだわる
今でこそ企業による寄付などもあり安定した運営ができているものの、立ち上げ当初のつばめ塾の財政は厳しい状況にあった。3人の子を持つ父である小宮氏は、正社員の仕事を手放してつばめ塾に専念してからは、自分自身が経済的に厳しい状況に陥ったという。
それでも無料塾にこだわるのは、小宮氏自身が経済的に苦しい家庭で育ったからだ。都立高校3年の時には、当時の授業料の月額1万1000円が支払えずに中退の危機に直面。奨学金を申請して卒業し、大学の入学金や授業料は母方の祖父母に頼み込んで何とか工面できたが、しばらくは教科書を購入できなかったという。